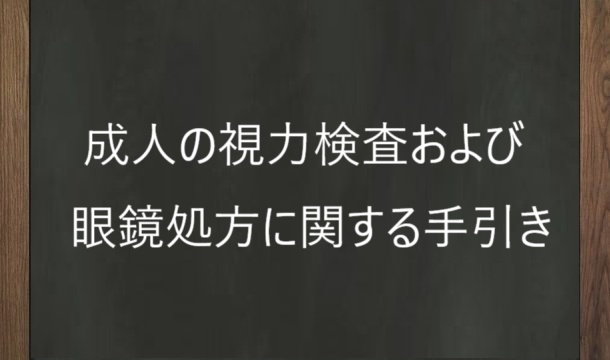もくじ
成人の視力検査および眼鏡処方に関する手引き
スポンサーリンク
1.成人の視力検査・眼鏡処方のコンセプト
2)適切な眼鏡とは
- 強い近視や斜乱視をそのまま矯正すると、歪みが生じて装用に耐えられないことがある。
4.眼鏡処方の実際(非疾患眼)
2)近視(単純近視)
- 瞳孔径が1~2 mm以下(ピンホール)では、回折による視力低下がみられる。近視強度0.00~-1.00Dではいずれの場合も,瞳孔径2 mmで視力のピークに達する。さらに瞳孔径が大きくなると、徐々に視力は低下する。ここで近視強度-1.00Dに注目すると、瞳孔径2~3 mm、つまり明所においては0.7以上の視力がみられる.しかし、雨天や夜間で瞳孔径が4~6 mmになると、視力は0.5以下となる。一方、近視強度-0.50Dでは、瞳孔径1~5 mmの広い範囲で、0.7以上の視力が確保できる。実際には乱視の影響が加わるため話は単純ではないが、照度を問わず常時良好な視力を確保するには、屈折度数-0.75~-1.00Dが、眼鏡矯正のタイミングを考える一つの目安となる。
- 近視眼鏡を低矯正で処方すべき症例も存在する。
- 完全矯正眼鏡を装用させたときに、近見で内斜偏位を示す症例。調節性輻湊が強い、つまり調節性輻湊対調節比(accommodative convergence/accommodation ratio:AC/A 比)が高い症例。内斜偏位に対しては運動性の輻湊(開散)性融像による代償が働きにくく、複視や眼精疲労の原因になることが多い。
- 第二は、老視の初期など、調節の機能不全がみられる症例。低矯正で近視矯正眼鏡を処方すると、低矯正の量だけ近見作業時の調節必要量を軽減できる。遠見での眼鏡視力は犠牲になるが、引き換えに近見作業は楽になる。しかし、この方法には限界があるので、老視が進めば、近用眼鏡との併用や累進屈折力眼鏡の処方を考慮する。
- 第三に、低視力者(ロービジョン)では一般に調節反応が乏しく、近視を完全矯正すると、近見作業時の調節ラグが増大する。他方で低視力者は、焦点誤差が生じても、網膜像のボケを認知しにくいため、健常者よりも広いDOFを備えていると見なすことができる。DOFの範囲内で近視を低矯正で処方することにより、遠見視力を維持しながら、同時に近見での眼鏡視力を改善できる。
5.眼鏡処方の実際(病眼)
2)偽水晶体眼
眼内レンズについては、支持部と光学部が一定の角度を持つ3ピース眼内レンズよりも1ピース眼内レンズのほうが屈折の安定が早いと報告されている。近年の報告では、合併症のない白内障手術の屈折は術後1~2週で安定するとの報告が多い。さらに視力の安定時期などを考慮すると、眼鏡処方は術後4週程度を目安にすべきである。