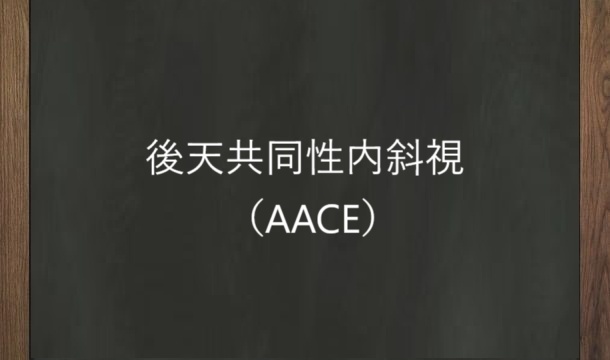もくじ
後天共同性内斜視とは
後天共同性内斜視とは、出生後に生じる共同性(注視方向によって斜視角がほぼ一定の、麻痺がない)内斜視を指し、小児から成人まで幅広い年齢で発症します。小児では屈折異常に関連した調節性内斜視が典型で、平均発症年齢は2~3歳とされています。小児の内斜視では最も一般的なタイプの一つです。
また、生後6か月以内に発症する乳児内斜視は除外され、6か月以降に発症する内斜視が後天性に分類されます。後天共同性内斜視は年長児~青年期(学童期以降)にも見られ、この年代で突然発症する急性後天共同性内斜視 (acute acquired comitant esotropia, AACE) は比較的まれですが、近年症例数の増加が報告されています。
日本における全国調査研究では、5~35歳の後天共同性内斜視患者の発症年齢は思春期の16歳をピークに中高生で頻度が高いことが明らかとなりました。この研究では、斜視や弱視の既往、不同視(左右視力差)のある人で発症しやすい傾向も示されています。性差に関しては男女差はないとされ、男女いずれも発症し得ます。
罹患率は年齢層によって異なり、小児の斜視全体に占める割合は報告により異なりますが、例えば急性後天共同性内斜視(AACE)は小児の斜視患者の約0.3%とかなり稀であるとの報告があります。一方で、学童期以降の調節非依存性の内斜視(非調節性内斜視)は小児内斜視の約10~20%程度とされています。地域差として、欧米では内斜視の方が多い傾向がある一方、東アジアでは外斜視の有病率が相対的に高いという報告もあり、人種や屈折傾向による差異も示唆されています。
近年、デジタルデバイスの長時間使用との関連で、学童期~若年成人の後天共同性内斜視が増加していることが注目されています。COVID-19パンデミック下でのオンライン授業や自宅生活の影響もあり、この10年で急性内斜視の報告数が急増しました。実際、デジタルデバイス過剰使用と急性内斜視との関連を調べた日本の多施設研究では、スマートフォンなどの使用時間を指導により半減させたところ患者の44%で斜視角が改善し、6%は自然治癒に至ったと報告されています。
このように、後天共同性内斜視の疫学は時代と生活環境の変化によって動態が変わりつつあり、特に思春期世代での発症増加が近年のトピックとなっています。
後天共同性内斜視の病因と病態生理
後天共同性内斜視の原因は多岐にわたり、大きく屈折異常に伴うものと屈折異常以外の要因に分けられます。屈折異常では遠視(特に調節性内斜視)が代表で、遠視があるとピント合わせのための調節に伴う過度の輻輳反射が起こり眼位が内側に偏位します。調節性内斜視では通常+2~+6ジオプトリ程度の遠視が潜在しており、完全矯正眼鏡装用で正位に矯正されます。
一方、遠視が軽度であってもAC/A比が高い(調節に対する輻輳反応が過剰)場合、近見時に内斜視が強くなる非屈折調節性内斜視が生じ得ます。これら調節要因による内斜視は幼児期に徐々に出現することが多く、最初は間欠的な内斜視(ときに遠見では正常で近見のみ斜視)から始まり、放置すると恒常性の内斜視へ進行します。
視機能異常も内斜視の病因となりえます。幼少期に一眼の視力低下(重度不同視や白内障など)や眼帯遮蔽などで両眼視機能が障害されると、融像ができなくなった目が内方に偏位することがあります。このタイプは感覚性内斜視とも呼ばれ、Swan型(タイプI)内斜視として分類されます。
Swan型は1947年にSwanが初めて記載したもので、片眼遮蔽や視力喪失による急激な融像障害が引き金となる急性内斜視です。また、元々わずかな潜在性内斜視(内斜位)を有していた症例で、何らかの契機に融像予備力が破綻し顕性の内斜視に転じる場合があります。
これを融像不全型や徐々に進行する後天性内斜視と呼ぶことがあり、ストレスや体調不良などが誘因となって起こることがあります。Burianらの分類ではFranceschetti型(タイプII)に相当し、屈折異常が軽度で斜角が大きく、精神的・肉体的ストレスなど誘因が推測される突発性の共同性内斜視像として記載されています。Franceschetti型では遠視はあっても軽度で調節要因だけでは説明できない大角度の内斜視が生じ、患者は明瞭な複視を自覚することが多い点が特徴です。
もう一つ注目される病因が近業作業による調節緊張です。もともと中等度の近視でメガネを外して近見作業を長時間行うような場合、遠見と近見での輻輳・開散バランスが崩れて内斜視が生じることがあります。これはBielschowsky型(タイプIII)急性後天内斜視として古くから報告されてきたもので、ドイツのBielschowskyが1922年に記載した症例では近視約5ジオプトリの成人が急激な内斜視と複視を呈しました。
彼は「近視の患者が眼鏡を外して極度に近距離で読書や作業を行うと、輻輳と開散のバランスが崩れ内直筋の緊張が増すことで内斜視が発生する」と推測しています。近年このメカニズムはデジタル機器長時間使用によるケースで再び注目されており、スマートフォン等を顔に近づけて長時間見る習慣がAACEを誘発しうることが報告されています。これは内直筋のトーヌスの増強や近見反応、調節への負担の増大、開散の異常によって引き起こされると考えられています。
また、まれな要因ですが、神経学的異常も後天共同性内斜視の病因となります。特徴的なのは急性小脳障害や脳幹病変による場合で、例えばキアリ奇形(小脳扁桃下垂)や脳腫瘍が最初の徴候として急性の共同性内斜視を呈しうることがあります。この場合、多くは他に頭痛や眼振、小脳症状など随伴症状を伴うため鑑別の手掛かりとなります。
輻輳痙攣(過度輻輳による偽内斜視)も中枢神経要因として鑑別すべき状態で、これは実際には調節と輻輳の過剰亢進による一過性の内斜視であり、心理的要因や中脳障害(Parinaud症候群など)で生じます。輻輳痙攣では瞳孔縮小や調節痙攣を伴うことが多く、真の共同性内斜視とは区別されます。
また中高年以降では加齢性変化により外転作用が低下して徐々に内斜視が出現することがあります。近年Sagging Eye Syndromeと呼ばれる眼球支持組織の加齢変性による眼位異常が注目されており、高齢者で輻輳不全型内斜視(遠見での内斜視)を呈する原因として報告されています。この場合、眼瞼下垂や軽度の下斜位を伴うこともあり、一見共同性内斜視に見えても画像検査で外直筋の位置変化など構造的異常が確認されます。
以上のように、後天共同性内斜視の病因は屈折異常(遠視)による調節過剰、融像の破綻、近見負荷、潜在斜視の代償不全、中枢神経疾患など多岐にわたります。その病態生理は、眼球運動や両眼視機能のバランスが何らかの要因で崩れることで両眼視が維持できなくなり、内側への偏位(内斜視)が恒常化することにあります。一方で外眼筋自体の麻痺や拘縮がないため、眼球運動制限を伴わず全方向でほぼ同程度の斜視角(共同性)を示す点が特徴です。後天共同性内斜視の大部分は良性の特発性ないし屈折関連のものであり、多くの症例で明確な脳神経疾患等は認められません。しかし、小児の急性発症例や、神経学的症候を伴う例では中枢疾患の可能性を念頭に置く必要があります。
後天共同性内斜視の症状
後天共同性内斜視の臨床症状は、発症年齢や経過によって大きく異なります。徐々に発症するタイプでは、初期には時折寄り目になる程度の間欠性内斜視から始まり、しだいに頻度が増して恒常性になります。
小児の調節性内斜視が典型例で、保護者が写真や日常観察で「ときどき片眼が内側に寄っている」ことに気付き受診するケースが多くみられます。幼児~小児は複視を自覚しにくく、片眼視を抑制する適応が働くため症状を訴えないこともしばしばあります。その結果、片眼の視力発達が阻害され弱視となって発見される例もあります。
一方、学童期以降になると両眼視機能が成熟しているため、今まで正位で両眼視していた人が急に内斜視になると複視を自覚するのが通常です。特に急性後天共同性内斜視では、「ある日突然ものが二重に見え始めた」といった訴えで受診します。この急性型では眼球運動は正常で、片眼遮閉をすると複視は消失するという訴えがあります。若年者では複視の自覚があいまいな場合もありますが、成人では強い複視により日常生活に支障を来すため早期受診する傾向があります。
後天共同性内斜視の分類
後天共同性内斜視は臨床経過によりいくつかの亜型に分類されます。緩徐発症型は上述のように徐々に内斜視が顕在化・増大するタイプで、調節性内斜視や思春期に発症する特発性内斜視の多くが該当します。
急性発症型(AACE)は文字通り数日~数週間以内という短期間で内斜視が成立するタイプで、斜視角も比較的大きく、複視を伴うことが多い点が特徴です。急性型AACEはさらに原因別に前述のSwan型・Franceschetti型・Bielschowsky型などに細分類されます。
例えば、ある日片眼を遮蔽して過ごした後に急に斜視が出現した場合はSwan型、特にきっかけ無くストレス下で突如複視と大角度内斜視を呈した場合はFranceschetti型、高度近業後に遠見で強い内斜視になった場合はBielschowsky型、といった具合です。臨床的にこれらを厳密に分類できないケースも多く、複合要因のこともありますが、いずれも眼球運動は正常で外転制限を伴わない内斜視であることが診断上のポイントです。
| Burianらの分類 |
| Ⅰ型(Swan type):片眼の遮閉や視力低下による融像の遮断が関連するもの |
| Ⅱ型(Burian-Franceschetti type):原因不明で、心身のストレスを伴うことがあるもの |
| Ⅲ型(Bielschowsky type):-5Dより強度近視とその低矯正が関連するもの |
| Buchらの分類 |
| 調節性のもの |
| 単眼固視症候群あるいは内斜位の代償不全によるもの |
| 特発性のもの |
| 頭蓋内病変を伴うもの |
| 遮閉に関連するもの |
| 他の病気に続発するもの(視神経炎など) |
| 周期性のもの |
| von Noordenらの分類 |
| 人工的な両眼視の遮断によるもの |
| 内斜位の代償不全によるもの |
| 中枢神経系の異常に伴うもの |
後天共同性内斜視の検査および診断
後天共同性内斜視が疑われる患者には、いくつかの眼科検査が必要です。まず視力検査を行い、特に小児では弱視の有無をチェックします。次に屈折検査(散瞳下屈折検査)を行い、遠視の有無と程度を正確に測定します。
急性発症の内斜視であっても軽度の遠視が潜んでいる場合があり、適切な屈折矯正が診断と治療双方に重要です。屈折異常が判明した場合、それを矯正した状態で眼位検査を進めます。
カバーテスト
眼位の評価では、カバーテストが基本です。単眼遮蔽・交代遮蔽試験により、内斜視の有無と程度(偏位角)を確認します。定量的な偏位角測定にはプリズム遮閉試験を用い、遠見(6m)と近見(33cm)の両方で斜視角を測定します。これにより遠見と近見の角度差(AC/A比の臨床的指標)が分かり、調節要因の寄与を評価できます。可能であれば9方向(主要注視位すべて)で斜視角を測定し、斜視角がどの方向でもほぼ一定であること(=共同性)を確認します。
また、眼球運動の他覚的な制限がないかバランスよくチェックし、外転神経麻痺などの所見がないことを確認します。必要に応じてヘルシュベルグ試験(角膜反射位置)やクリムスキー法(プリズム補正)を併用すれば、小児でもおおよその斜視角を推定できます。眼位写真を記録しておくことも経過比較に有用です。
両眼視機能
両眼視機能の評価も診断に重要です。複視の自覚がある場合、その像の上下左右関係から麻痺の有無を類推します。複視を訴えない小児ではWorth4灯検査やBagolini線条ガラス試験で抑制の有無を調べます。抑制が強い場合、小角度の斜視だとカバーテストで捉えにくいこともあるため、4プリズムベースアウトテストで微小斜視を検出することもあります。また、立体視検査を行い、特に小児では年齢相応の立体視があるか確認します。
急性後天内斜視の場合、発症早期であれば立体視がまだ保たれているケースもあり、予後予測の一助となります。実際、先述の日本の研究でも初診時に立体視が残存していた患者の方が非残存の患者より予後改善しやすかったことが報告されています。
MRI
MRI検査は脳幹部や後頭蓋窩の評価に有用で、急性共同性内斜視の一部に中枢神経疾患(脳腫瘍やChiari奇形など)がありうるため、臨床像が典型的でない場合や神経学的所見を伴う場合には施行が推奨されます。患者の年齢が高い成人例でも、突然の共同性内斜視+複視はまずMRIで中枢病変を除外するのが安全策です。特に40代以降の新規内斜視では軽度の外転神経麻痺との鑑別が難しいケースもあり、経過観察中に進行すれば追加検査を考慮します。
後天共同性内斜視の治療
後天共同性内斜視の治療は、原因と斜視角の大きさ、患者の年齢・症状に応じて段階的に行います。基本的な戦略は眼位を整えて両眼視機能を可能な限り回復させることです。そのために屈折矯正・プリズム補正・視能訓練・手術療法・ボツリヌス毒素などを組み合わせます。
眼鏡矯正
まず屈折異常がある場合、まずは適切な眼鏡矯正を行います。遠視があれば可能な限り完全矯正を処方し、調節性要因があれば内斜視が劇的に改善することも期待できます。AC/A比の高いタイプでは遠用と近用で眼位差が残ることがあるため、その場合は二重焦点眼鏡を処方し近見時の内斜視を矯正します。
眼鏡処方のみで正位を維持できれば、定期フォローの下で弱視治療(必要ならアイパッチによる遮蔽訓練)や経過観察を行います。特に調節性内斜視の場合、眼鏡装用だけで両眼視が再確立し正常立体視が得られることが多いため、早期の適切な屈折矯正が重要です。眼鏡処方の開始が遅れると、一部が非調節性内斜視へ移行して眼鏡だけでは治らなくなる割合が増えることも報告されています。
プリズム補正
眼鏡矯正後も内斜視が残存する場合や、そもそも屈折異常が関与しない内斜視では、プリズム補正や視能訓練による保存療法を検討します。複視が強い場合、速やかにプリズム眼鏡で複視像を融合させてあげると患者の負担が軽減します。フレネル膜プリズムを用いれば容易に度数調整が可能であり、急性期の一時的措置として有用です。プリズム効果で複視が解消すると融像が再獲得され、斜視角そのものが減少することが期待できます。
効果が出た場合はプリズム度数を段階的に下げていき、最終的にプリズムなしでも正位を保てれば治癒となります。一方、斜視角が大きい場合やプリズム装用で複視が解消しない場合は、この方法だけでは困難です。
手術
手術は、後天共同性内斜視における主要な治療です。屈折矯正やプリズムでも十分に改善しない大角度の内斜視では外眼筋手術による恒久的な眼位矯正が適応となります。基本術式は内直筋後転術で、両眼の内直筋を後転することが多いです。斜視角によって手術量を決定し、必要に応じて片眼に後転+外直筋短縮(Recession + Resection)を行います。
小児では全身麻酔下での手術となりますが、一般に安全かつ確立された手技であり、多くの症例で眼位の著明な改善が得られます。急性発症の共同性内斜視では、通常の量より後転量を0.5~1.0mm程度増量する修正術式が有効との報告もあります。これは急性内斜視では斜視角の変動が少なくないため、やや過矯正気味に手術することで再発を防ぐ目的があります。
また成人例では局所麻酔下に調節可能糸を用いて術後に微調整を行う方法も選択できます。手術の成功率はおおむね高く、例えばAACE患者に対する一般的な手術の成功率は80~90%と報告されています。一部で再発や残余内斜視があり追加手術が必要となるケースもありますが、適切な手術時期と術式の選択により多くの患者で両眼視復位が可能です。
なお、小児では弱視治療との並行、成人では複視に対する脳の適応(融像)の考慮が必要であり、術前後には眼鏡処方やプリズム補正を補助的に組み合わせることもあります。
ボトックス注射
近年、手術の代替あるいは補助としてボツリヌス毒素注射(ボトックス治療)が注目されています。これは12歳以上で保険適用になっており、内直筋にボツリヌス毒素A型製剤を注射し、一時的に筋力を弱化させて眼位を矯正する方法です。注射は局所麻酔下に外来で行えるため低侵襲であり、特に全身麻酔リスクを避けたい成人患者や、小児でも手術前の暫定措置として用いられます。
ボツリヌス療法の効果は一過性(通常3か月程度で消失)ですが、その間に融像が確立すると恒常的な正位が得られることがあります。
実際の有効性について、AACE患者を対象にボツリヌス両内直筋注射と手術を比較した前向き研究では、ボツリヌス群40例中初回治癒率95%・再発率22.5%、手術群20例中初回治癒率75%・再発率20%であり、両者の成績に有意差はなかったと報告されています。特に、14歳未満の小児9例では全例がボツリヌス治療のみで正位を獲得し再発も見られなかったとの報告で、一定の効果が示されています。
ボツリヌス注射の利点は、全身麻酔を回避できること、治療コストが低減すること、両眼視獲得までの時間を短縮できる可能性があることです。さらに、手術と異なり筋の侵襲が少ないため将来的な手術にも悪影響を与えにくいと考えられます。ただし、一部では効果不十分で結局手術が必要になるケースや、注射による一過性の眼瞼下垂・斜位の過矯正などの副作用も報告されています。したがって症例選択と適切な投与量の判断が重要です。
後天共同性内斜視の合併症と予後
後天共同性内斜視そのものは命に関わる疾患ではありませんが、適切に対処しないと視機能の発達や日常生活の質(QOL)に重大な影響を及ぼします。小児例では弱視と立体視の未発達が主な合併症です。
内斜視の約半数の小児が弱視を呈するとの報告もあり、斜視によって抑制が生じると健眼優位になり斜視眼の視力発達が阻害されます。さらに両眼視が確立しないと立体視が得られず、将来的な職業選択や運動能力にも影響しえます。したがって幼少期に発症した内斜視では、眼位矯正だけでなく弱視治療を含めた視力管理が不可欠です。
早期に正位を獲得できれば両眼視機能が正常化し、立体視も良好に発達します。実際、急性後天内斜視の治療例では適切な治療介入により大部分の患者で正常な両眼視と立体視が回復しています。一例として、AACE患者30例中29例(96.7%)が手術や眼鏡治療後に正常な両眼視機能と眼位を維持できたとの報告があります。逆に治療が遅れると融像不全が固定化し、斜視を矯正しても立体視が獲得できない場合があります。そのため、小児の内斜視は発症早期から適切に管理し、できるだけ学童前までに両眼視を確立させることが望ましいです。
成人例では弱視の心配はありませんが、複視による日常生活障害が深刻な問題となります。急に内斜視になった成人は常に二重像が見えるため、運転や読書が困難になり、頭痛や眼精疲労を訴えます。この複視は眼位が矯正されると消失しますが、それまでの間はプリズム眼鏡や片眼遮閉で対症療法をとる必要があります。
また心理社会的にも、斜視の外見が仕事や対人関係のストレスとなり得ます。したがって成人発症の内斜視では、可能な限り早期にプリズム補正や手術で複視を解消し、患者のQOL低下期間を短縮することが重要です。
予後としては、多くの成人例で治療により複視が消失し社会復帰できますが、発症から治療までの期間が長いと融像の再獲得に時間がかかることがあります。一部では、手術で正位になっても脳が適応できずに残像視が持続したり、融像負荷により眼精疲労が残るケースもあります。ただし大半の患者では数週間~数ヶ月で脳が新しい眼位に適応し、快適な単一視が得られます。
手術治療を行った場合の予後については、適切な眼位が得られたか、両眼視が復活したかを確認します。多くの症例で初回手術で目標を達成できますが、斜視角が大きかった例や発症から時間が経っていた例では再手術や追加治療が必要になることもあります。
また、手術の合併症として、過矯正により外斜視に転じてしまうことがあります。これを続発性外斜視と呼び、内斜視手術後の5~15%程度で生じ得るとされています。続発性外斜視が小角度で両眼視が保たれていれば経過観察しますが、大きい場合はプリズム補正や追加手術で整復します。特に乳幼児期早期に手術した先天内斜視では、思春期以降に外斜視へ転じる例が少なくなく、長期フォローが望まれます。
後天共同性内斜視の手術成績自体は良好ですが、一度の手術で一生安定とは限らず、経年的な変化で再度の眼位ずれが生じる可能性があります。定期的な経過観察により、必要に応じて追加矯正のタイミングを判断することが理想的です。
良好な予後因子としては、発症年齢が高すぎないこと、斜視角が極端に大きくないこと、初診時に立体視が残存していることなどが挙げられます。上記日本の研究でも、デジタル機器過剰使用群の若年患者で初診時に立体視があった人ほど非侵襲的治療で改善しやすかったとされています。一方、予後不良因子としては発症年齢の高齢化、治療介入までの期間遅延、初期斜視角が大きいことなどが知られています。これらの知見は、後天共同性内斜視において早期発見・早期治療がいかに重要かを示唆しています。
参考文献
- Esotropia
- Acute acquired comitant esotropia: Current understanding of its etiological classification and treatment strategies
- 浜松医科大学の発表
- Esotropia
- Acute Acquired Comitant Esotropia: Etiology, Clinical Course, and Management
- Acute acquired comitant esotropia related to excessive Smartphone use
- 日本の眼科96:4号(2025)
- Treatment of acute acquired concomitant esotropia
- Accommodative esotropia: the state of the art
- Prismatic treatment of acute acquired concomitant esotropia of 25 prism diopters or less
- Botulinum toxin-A in acute acquired comitant esotropia during COVID pandemic in children and young adolescents
- Efficacy of botulinum toxin and surgery in managing acute acquired comitant esotropia