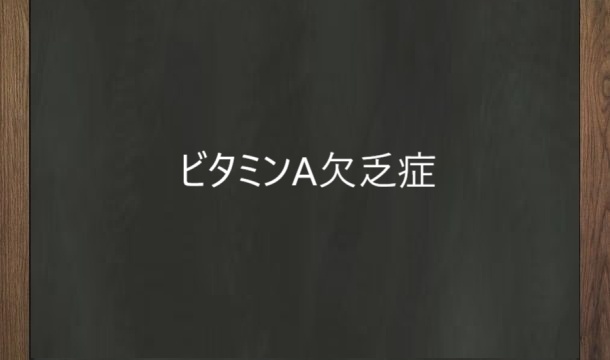もくじ
ビタミンA欠乏症
細隙灯顕微鏡検査では結膜の異常な光沢を認める。また、慢性的ビタミンA欠乏症の患者ではBitot斑が観察される。Bitot斑は輪部に隣接する鼻側、耳側結膜に形成される白色隆起した病変で、結膜上皮の角化病変である。白色を呈する炭水化物への偏りが顕著である。米やジャガイモ、白色煎餅のみを好み、色のついたふりかけなどを添加すると食べなくなるなど。ERGにおいてβ波の減弱・消失などの杆体細胞機能低下の測定や、視野検査による視野の進行性縮小の評価が役立つ。
ビタミンAに加えそれ以外のビタミンC、D、E、K、ビタミンB群(とくにB₆、B₁₂、葉酸)やカルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄などのミネラルの測定も行う。血中のビタミンA濃度が20μg/dl(70μIU/dl)未満であれば、小児ではビタミンA欠乏症の懸念があると報告されている。
ビタミンAの測定には、間接的な検査として血漿蛋白と結合しているレチノイド結合蛋白を測定する方法と、外部委託し直接測定する方法があり、ビタミンA欠乏症の確定診断とともに治療中と治療後のモニタリングに有用である。
ビタミンA欠乏症は単独ではなく複合的な栄養素欠乏を伴うことが多く、マルチビタミン・ミネラル、亜鉛、鉄分、オメガ3脂肪酸などの包括的な補充も重要である。特に、亜鉛はビタミンA代謝を促進し、鉄分は貧血の改善に役立つ。
治療は対症療法に加え、角膜上皮の再生促進のための自己血清点眼や、進行例では羊膜移植や角膜移植も検討されるが、乳幼児では外科的治療の予後は一般に不良であると考えられている。角膜混濁や視神経萎縮をきたしていない場合は、ビタミンAの補充により週単位で改善し視機能の回復が期待できる。一方、長期間の重度ビタミンA欠乏状態から生じた角膜瘢痕や視神経萎縮は、不可逆的な視力障害を残す可能性がある。