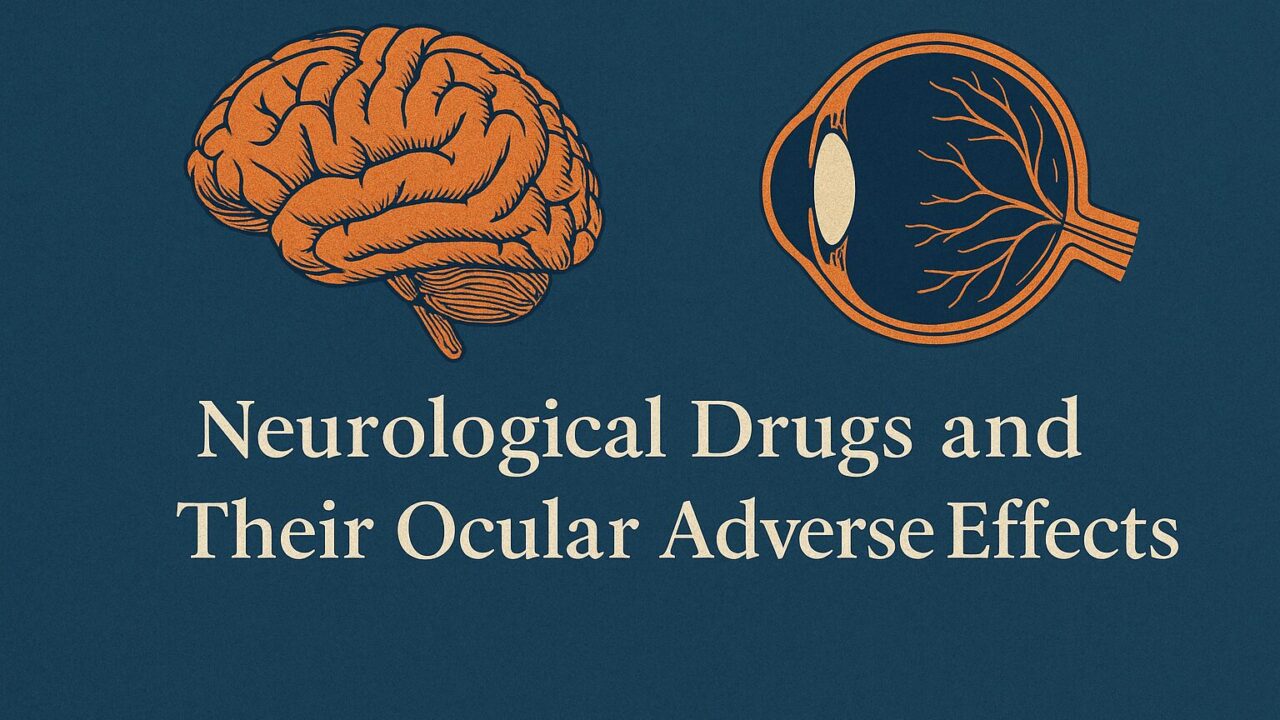脳神経内科では、生物学的製剤や抗てんかん薬など新しい薬剤が次々と登場しており、それに伴って眼科領域での副作用も注目されています。眼科医にとっては日常診療の中で見逃せない問題であり、薬剤性を疑う姿勢が重要です。薬の中止や治療変更が必要になる場合もあり、眼科医と神経内科医の連携が不可欠とされています。
もくじ
抗てんかん薬による眼障害
新規の抗てんかん薬の使用拡大により、眼障害の報告も増加しています。特に注意が必要なのは、薬剤アレルギー反応の一種である Stevens-Johnson症候群(SJS)や中毒性表皮壊死症(TEN) です。これらは結膜炎や角膜障害を引き起こし、重篤な視機能障害につながります。
治療にはステロイド療法や免疫グロブリン静注(IVIg)が行われます。また、ビガバトリン(サブリル®)は小児てんかん薬ですが、長期内服で不可逆的な視野狭窄、錐体機能障害、視神経萎縮を認めることがあります。そのため、定期的な視野検査などが必須となっています。
神経難病治療薬と眼障害
1. 副腎皮質ステロイド
神経難病の急性期治療に頻用される副腎皮質ステロイドは、視神経脊髄炎や重症筋無力症などの治療に欠かせない薬剤です。しかしその一方で、長期投与により白内障や緑内障を誘発することが知られています。また、免疫抑制作用による感染症の悪化や、糖尿病・高血圧・骨粗鬆症などの全身的副作用に加え、眼領域でも合併症をきたすため、定期的な眼科フォローが推奨されます。
2. インターフェロン(IFN)
IFNは主に多発性硬化症(MS)の再発予防やウイルス性疾患に使用されます。眼科領域では特に IFN網膜症 が問題となります。投与開始2週間〜5か月の間に多く発症し、網膜出血や白斑、視力低下を生じます。発症率は18〜86%と幅広く、糖尿病や高血圧、肝疾患のある患者でリスクが高まります。
多くは一過性で投与中止により改善しますが、重症例では不可逆的な視覚障害を残すこともあるため、眼底検査などの定期的なモニタリングが必須です。
3. フィンゴリモド塩酸塩
フィンゴリモドは、MS(多発性硬化症)の治療に用いられる経口薬で、免疫調整作用をもつ新規薬剤です。しかし、その副作用として フィンゴリモド関連黄斑浮腫(FAME: fingolimod-associated macular edema) が知られており、霧視や視力低下の原因となります。発症頻度は0.1〜0.6%と比較的低いものの、導入3〜4か月までに多く発症すると報告されています。
発症リスクと注意すべき患者背景
FAMEは、糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症などの既往を持つ患者で発症しやすいことが分かっています。こうした基礎疾患を抱える場合は、フィンゴリモドの導入自体を慎重に検討する必要があります。
モニタリングと診療体制
FAMEの早期発見には、眼底検査や光干渉断層計(OCT)を用いた詳細な網膜検査が有効です。実臨床では投与開始前と導入後1、3、6か月後、それ以後は6か月ごと定期的な視力検査や眼圧検査、眼底検査などが推奨されます。また、ガイドラインでは、フィンゴリモド投与に際して 眼科との連携体制が整っていること を前提条件(施設要件)としています。
治療と対応
FAMEが発症した場合、原則としてフィンゴリモドを中止し、視力回復を図ります。軽症例では自然軽快することもありますが、重症例では硝子体内注射(トリアムシノロン)などを行う場合もあります。
4.シポニモドフマル酸(メーゼント)
新しいS1P受容体調節薬としての登場
シポニモドフマル酸(商品名メーゼント)は、2020年6月に日本で承認された新規薬剤です。対象は 二次性進行型多発性硬化症(SPMS) で、再発予防や身体機能障害の進行抑制に効果があります。投与は漸増法で開始され、最終的に維持量2mgを1日1回内服します。
眼領域での副作用 ― 黄斑浮腫
シポニモドの眼科的副作用として注目されるのは 黄斑浮腫 です。発症頻度は約1.3%とされ、特に投与初期に出現しやすいとされています。黄斑浮腫は軽症例から重症例まで幅広く、重症例では失明リスクもあるため、早期発見が重要です。
特に糖尿病やぶどう膜炎などの既往がある患者は発症リスクが高いため、投与前の眼科検査および投与中の定期的なフォローが必須です。
対応と管理
重度の黄斑浮腫が出現した場合には、原則としてメーゼントの投与中止が基本対応となります。そのうえで有益性と危険性を総合的に評価し、必要に応じて付加治療を行います。治療継続の可否を判断するには、眼科医との緊密な連携が不可欠です。
5.ナタリズマブ(タイサブリ)
薬剤の特徴
ナタリズマブは、多発性硬化症(MS)の再発予防や身体機能障害の進行抑制を目的に使用される薬剤です。通常、成人には 300mgを4週ごとに点滴静注 で投与されます。作用機序は、α4β1インテグリンが血管内皮のVCAM-1に結合するのを阻害し、炎症細胞が中枢神経へ侵入するのを防ぐことで免疫反応を抑制します。
全身および眼への副作用
有効性の高い一方で、副作用として 進行性多巣性白質脳症(PML) が知られており、定期的な神経学的評価が欠かせません。眼領域における注意点としては、
- 網膜壊死(acute retinal necrosis: ARN)
-
黄斑変性
が報告されています。ARNは急速に進行し、失明に至るケースもあるため、視力低下や霧視、眼痛などの症状が出た場合は、直ちにナタリズマブを中止して眼科的精査を受けることが推奨されます。
管理と対応
ナタリズマブ投与中に視覚症状が出現した場合には、眼科でのARNの有無の確認が最も重要です。必要に応じて抗ウイルス薬や硝子体内注射などの治療が検討されます。迅速な診断と適切な対応が予後を左右するため、神経内科と眼科の緊密な連携が不可欠です。
6.アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
薬剤の特徴
アセチルコリンエステラーゼ阻害薬は、重症筋無力症 や Alzheimer病 の治療に広く用いられる薬剤です。アセチルコリンは神経伝達物質の一つで、神経終末から放出されシナプス間隙で作用しますが、アセチルコリンエステラーゼによって速やかに分解されます。阻害薬はこの酵素活性を抑制することで、神経終末部でのアセチルコリン濃度を上昇させ、神経伝達を強める効果を発揮します。
副作用と眼への影響
過剰投与時には全身性副作用として 下痢、腹痛、嘔気、発汗、徐脈、呼吸困難 などが生じます。眼科領域における特徴的な副作用としては、
- 縮瞳(強い瞳孔収縮)
-
毛様体筋の過緊張による近視化
が挙げられます。これにより視力低下や眼精疲労が出現することがあり、特に中毒量では著明な縮瞳と調節けいれんを認めることがあります。
片頭痛治療薬と眼副作用
1. エルゴタミン製剤
かつては片頭痛の急性期治療薬として広く使用されていたエルゴタミン製剤ですが、現在は トリプタン製剤の普及 により使用頻度は大きく減少しています。この薬は強い血管収縮作用を持つため、稀に 網膜静脈閉塞症 を引き起こすことがあります。眼科的には視力低下や視野欠損などのリスクに注意が必要です。
2. アミトリプチリン
片頭痛や緊張型頭痛の 予防薬 として用いられる三環系抗うつ薬アミトリプチリンは、中枢神経系や自律神経系への作用により以下の副作用が出現します。
- 眠気、めまい、口渇、便秘、排尿困難
-
眼科領域では 眼圧上昇
特に緑内障を有する患者では眼圧上昇が重篤化する可能性があり、注意が求められます。
Parkinson病治療薬と眼副作用
薬剤の特徴
Parkinson病の初期症状(振戦など)に対して用いられる薬剤のひとつに、抗コリン薬(副交感神経遮断薬)であるトリヘキシフェニジル塩酸塩 があります。この薬は神経伝達に関与するアセチルコリンの作用を抑制することで、運動症状の改善を目的に使用されます。
副作用と眼への影響
高齢者では特に副作用が出やすく、長期間の使用により 眼調節障害(ピント合わせが難しくなる状態)が起こります。さらに眼科領域における重大な副作用として、閉塞隅角緑内障の誘発 が知られています。そのため、トリヘキシフェニジルは 閉塞隅角緑内障の患者には禁忌 とされています。
参考文献
- Retinopathy in a multiple sclerosis patient undergoing interferon-therapy
- Retinopathy during interferon-β treatment for multiple sclerosis: case report and review of the literature
- Interferon-Induced Retinopathy
- Interferon-beta-1a induced retinopathy in a 14-year-old female patient with multiple sclerosis
- [Combined retinal artery and vein occlusions associated with interferon beta therapy]
- A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis
- Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis
- Comparison of fingolimod with interferon beta-1a in relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomised extension of the TRANSFORMS study
- Fingolimod-associated macular edema: incidence, detection, and management
- A randomized, controlled trial of fingolimod (FTY720) in Japanese patients with multiple sclerosis
- Does fingolimod in multiple sclerosis patients cause macular edema?