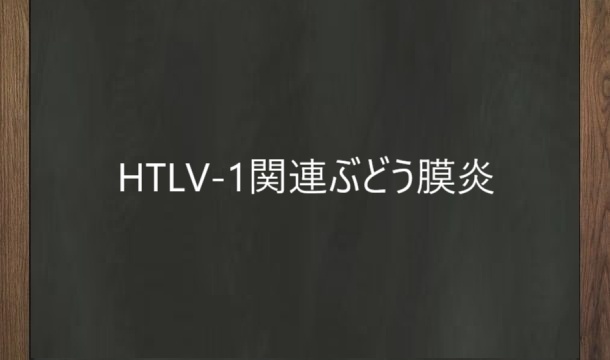HTLV-1関連ぶどう膜炎とは
HTLV-1関連ぶどう膜炎(HTLV-1-associated uveitis, HAU)は、HTLV-1ウイルス感染者(キャリア)において発症するぶどう膜炎です。HTLV-1感染症は世界で約2000万人の感染者がいると推計されており、日本南西部(九州地方)やメラネシア、カリブ海地域、中南米、中部アフリカなどに感染者が多く分布します。HAUはこれらHTLV-1高蔓延地域で多く報告されています。
日本では全国的にはHAUはまれですが、地域差が顕著です。2009–2010年の全国36大学病院の前向き調査では、新規ぶどう膜炎患者3,830例中HAUは29例のみ(全体の約0.8%)でした。一方で、HTLV-1感染者が多い南九州の宮崎県都城市の眼科では、2011–2014年のぶどう膜炎患者949例中HAUが135例と14.2%を占め、当地域では最も頻度の高いぶどう膜炎原因疾患でした。このようにHAUの患者数は地域により大きく異なり、特に九州南部に集中しています。
HTLV-1キャリアにおけるHAU発症の頻度は、おおよそ0.1%前後と推定されています。北部九州での研究では、HAUの有病率は約112人/10万人キャリア(男性59人、女性152人)と推定されており、これは同じHTLV-1関連疾患のHAM(脊髄症)よりやや高い値です。
HAUは女性に多い傾向があり、性比は報告により2~3.5:1で女性優位です。発症年齢は小児から高齢者まで幅広く分布しますが、ピークは女性50歳代、男性60歳代とされ、中年以降の発症が多くなります。これは主に母乳による垂直感染で幼少期に感染したキャリアが中高年になってから発症する例が多いためと考えられます。
また、HAU患者にはBasedow病の合併が注目されており、ある報告ではHAU患者135例中23例(17%)が甲状腺機能異常を有し、21例はぶどう膜炎発症前から甲状腺機能亢進症で治療中でした。この関連の機序は明らかでないものの、Basedow病の既往があるHTLV-1キャリアではHAU発症リスクが高まる可能性があります。
HTLV-1関連ぶどう膜炎の病態
HAUの病態はウイルス感染により誘導される免疫応答による炎症と考えられています。HTLV-1は主にCD4⁺Tリンパ球に感染するレトロウイルスであり、HAU患者の眼内からは多数のT細胞(CD3陽性T細胞)が浸潤細胞として検出されます。
浸潤細胞の解析により、これらは腫瘍化した白血病細胞ではなくHTLV-1に感染したT細胞クローンであることが確認されています。実際にHAU患者の眼内(前房や硝子体)からはHTLV-1のプロウイルスDNAやウイルス蛋白が検出されており、感染リンパ球が眼内に入り込んでいる証拠となっています。
さらに、眼内から樹立されたHTLV-1感染CD4⁺T細胞クローンはIL-1、IL-6、IL-8、TNF-α、IFN-γなど多様な炎症性サイトカインを大量に産生することが示されています。このため、HAUはHTLV-1感染CD4⁺T細胞が産生するサイトカインによって引き起こされるぶどう膜炎であると考えられています。
HTLV-1関連ぶどう膜炎の症状と所見
症状
HAUは急性発症することが多く、主な自覚症状は以下のとおりです:
-
霧視:初発症状として最も多く報告されます(約62%)。
-
飛蚊症:視野に虫やゴミが飛んでいるように見える症状で、硝子体中の浮遊物(炎症細胞や混濁)によるものです(約44%)。
-
視力低下:炎症や硝子体混濁、黄斑浮腫などによります(約44%)。
-
目の充血 – 強い前部ぶどう膜炎を伴う場合にみられ、充血や虹彩炎による疼痛・光過敏を呈することがあります(充血8%、眼痛2%、羞明<1%と報告)。
HAUでは片眼のみの場合と両眼に発症する場合があり、その頻度はほぼ同等です。一側の眼に急性のぶどう膜炎が起こり、その後もう一方の眼が別エピソードで罹患することもあります。
炎症の主座は汎ぶどう膜炎(前部・中間部・後部すべてに炎症が及ぶ)が約50%と最多で、次いで中間部ぶどう膜炎(硝子体主体)が29%、前部ぶどう膜炎が21%、後部ぶどう膜炎は極めて稀(1%)と報告されています。実際の臨床像としては虹彩炎と硝子体混濁を伴う急性ぶどう膜炎という形で現れ、眼底所見では硝子体混濁による飛蚊症のほか、網膜血管炎や乳頭浮腫様の所見が認められることがあります。
症状は適切な治療で数週~1ヶ月程度で寛解することが多いものの、約30%の患者で再発がみられます。再発は2~3回程度までのことが多いですが、なかには4~5回と繰り返す例もあります。再発の間隔は数ヶ月~数年と様々で、長期的な経過観察と患者教育(症状出現時の早期受診の指導)が重要です。
HTLV-1関連ぶどう膜炎の検査
HAUが疑われる患者では、眼科的検査と血液検査から評価を行います。
血清学的検査
HTLV-1キャリアかどうかを確認するために抗HTLV-1抗体検査を実施します。スクリーニングはPA法(粒子凝集法)やCLEIA法(化学発光酵素免疫測定法)で行われ、陽性例でウエスタンブロット法により確認されます。HAU患者では血清抗体陽性であることが必須ですが、抗体陽性=HAUではない点に注意が必要です。補助的にHTLV-1のプロウイルス量(末梢血中のHTLV-1感染細胞数)を測定することもあります。
眼科検査・画像検査
スリットランプで前房細胞や虹彩炎所見、硝子体混濁の有無を評価します。眼底検査では網膜周囲の炎症(血管炎)や黄斑浮腫の有無、視神経乳頭の発赤腫脹などを観察します。必要に応じて蛍光眼底造影(FA)を行い、網膜血管からの蛍光漏出(血管炎の指標)や乳頭漏出、黄斑部の浮腫を評価します。HAUでは網膜血管周囲の軽度の血管炎が認められることがありますが、他疾患に比べて特異的な所見は乏しく、サルコイドーシスやベーチェット病、Vogt-小柳-原田病などとの鑑別が問題になります。またHAU患者ではドライアイや角膜障害を合併することもあり、シルマー試験や角膜検査を行うこともあります。
前房水・硝子体液の検査
確定診断や他疾患除外のため、前房水や硝子体液を採取してウイルス検査を行うことがあります。PCR法によるHTLV-1プロウイルスDNAの検出率は高く、HAU患者の眼内液からはほぼ全例でHTLV-1のDNAが検出されたとの報告があります。
HTLV-1関連ぶどう膜炎の治療
HAUの治療は、基本的には他のぶどう膜炎と同様に炎症のコントロールが目的となり、第一選択は副腎皮質ステロイドの投与です。炎症の程度に応じて局所療法と全身療法を組み合わせます。
-
局所ステロイド療法:軽度~中等度の前部ぶどう膜炎を伴う場合はステロイド点眼を頻回投与し炎症を鎮静します。中間部・後部の炎症が強い場合にはテノン嚢下ステロイド注射や硝子体内トリアムシノロン注射を行うこともあります。局所療法でコントロールできれば全身への副作用を避けられるため、可能な限り局所ステロイドで十分な効果を得ることが望ましいです。
-
全身ステロイド療法:炎症が両眼に及ぶ場合や硝子体混濁が高度で視力低下が強い場合、局所療法で不十分な場合には経口ステロイドを併用します。プレドニゾロン換算で初期20~40mg程度から開始し、炎症の沈静化に応じて徐々に減量します。重症例(視力が著しく低下、網膜に高度の浮腫がある等)ではステロイドパルス療法(メチルプレドニゾロン静脈点滴 1000mgを3日間など)を行い急速に炎症を抑えることもあります。ステロイドに対する反応性はHAUでは良好なことが多く、適切な治療で1~2ヶ月以内に炎症寛解が得られるのが通常です。
-
免疫抑制剤の使用:HAUは多くの場合ステロイド単独でコントロール可能ですが、再発を繰り返す症例やステロイド副作用で十分な量を維持できない場合には、ステロイドスパリング目的で免疫抑制薬を検討します。一般的な非感染性ぶどう膜炎に準じてメトトレキサート、シクロスポリン、アザチオプリン、タクロリムスなどが選択肢となります。特にHAU患者では眼合併症として緑内障のリスクが高く、ステロイド長期使用による眼圧上昇は避けたいところです。免疫抑制剤の投与にあたっては、HTLV-1キャリアである点を考慮しなければなりません。免疫抑制によりHTLV-1感染細胞が増殖しATLへの進展リスクが理論的には懸念されるため、治療適応は慎重に判断し、必要最小限の投与量・期間にとどめることが推奨されます。
HTLV-1感染は、生命予後不良な白血病である成人T細胞白血病・リンパ腫(ATL)を生じ、ATL患者に眼病変が生じることがある。
-
抗ウイルス療法:現在、HAUに対してHTLV-1ウイルスそのものを排除・不活化する特異的な抗ウイルス薬は確立されていません。抗レトロウイルス薬(例えばAZT+インターフェロン)はATL治療に用いられることがありますが、HTLV-1キャリア状態そのものを根治する治療法は無く、HAUにおいてもウイルス量を下げる治療戦略は確立されていません。したがって現状ではステロイドなど免疫抑制的治療による対症療法が中心であり、「HTLV-1感染を予防すること」がHAU発症予防の根本策となります。
治療経過中は眼圧や白内障の進行、感染症の併発に注意しながらステロイドを漸減します。HAU自体はステロイドへの反応性が良好なため、多くの症例で初回治療により沈静化し、その後ステロイド減量~中止が可能です。再発した場合も同様にステロイドで寛解導入を図ります。HAUと診断された段階で、患者にはHAMやATLを合併していないか内科的検査を行い確認します。HAU単独であれば治療は眼科中心で問題ありませんが、HAMを合併している場合は神経内科との連携が必要です。
参考文献
- Human T-cell Lymphotropic Virus Type 1 Uveitis
- HTLV-1ぶどう膜炎
- HTLV-1 uveitis
- Period prevalence of uveitis in human T-lymphotropic virus 1 carriers versus noncarriers in a highly endemic area: The Nagasaki Islands Study