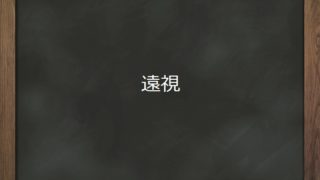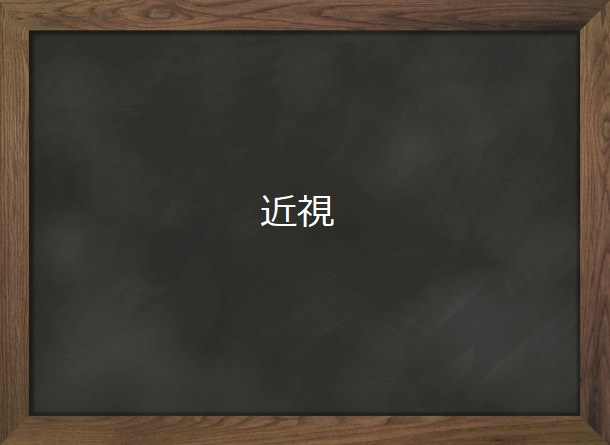もくじ
近視とは
「無調節状態で平行光線の焦点が網膜前方にある眼、または遠点が眼前方有限距離にある眼」と定義されている。この遠点に焦点が一致する凹(マイナス)レンズで矯正される。レンズから遠点までが焦点距離f(m)で、その逆数がレンズの屈折力(D)である。
2020年6月『日本の眼科』による発表によれば、視力1.0未満のうち近視だった割合は幼稚園で25.0%、小学校で78.4%、中学校で91.4%、高等学校で95.3%で近視が多く占める傾向にあった。
これは日本だけではなく、世界的にも近視人口が急増している。2016年にHoldenらは、これまで通りの増加が続けば、2050年には近視人口が全世界人口の半数に、強度近視も約1割に増加すると推定した。
各国の近視発症率調査結果(2005年以降、対象年齢6-7歳)
- Orinda Study(アメリカの白人):2.8%
- Northern Ireland Childhood Errors of Refraction(NICER)Study(イギリスの白人):2.2%
- Wang et al(中国都市部の東アジア系人種):19.1%
- Singapore Cohort Study of the Risk Factors for Myopia(SCORM):15.9%
- Sydney Myopia study(オーストラリアの同地域での近視発症の人種差):白人種1.3%、東アジア系人種6.9%
近視の発症・進行予測のリスク因子
- 遺伝的要因(片親が近視→2-3倍、両親が近視→5⁻6倍増加)
- 人種(東アジアで特に高い)
- 長時間の近業
- 2008年のIpJMらの報告によれば30分以上の連続した近業や30㎝以下の距離で近業は近視のリスクをそれぞれ1.5倍、2.5倍も増加させる。
- SCORMの報告によれば7~9歳では1週間に2冊以上の本を読むと3倍以上近視になりやすいことが分かった。
- Sydney Myopia studyでは11~14才で、近業時間が長いほど屈折値が有意に近視化したと報告されている。
- 屋外活動が短い(十分な屋外活動時間を確保すると、4~14才のアジア人の学童の近視発症が50%、進行が32.9%、眼軸進展が24.9%抑制できることが2019年のHoらのシステマティックレビュー、メタアナリシスで報告されている。推奨されるのは1000~3000Luxの照度が良いとされ、これは屋外であれば日陰でもその照度は担保される。
→1日2時間、少なくとも1時間以上の屋外活動が推奨されます。) - 両眼視機能
- 眼軸長
- 遠視度数(遠視度数の低下で将来の近視を予測することができるかもしれない。
6歳以下で+0.75D以下の遠視
7~8歳で+0.50D以下の遠視
9-10歳で+0.25D以下の遠視
11歳で+0.0Dあるいは、-0.5D以上の近視
が近視発症の高リスクとなる。)
など
近視の分類
- 屈折性近視:眼軸長が正常範囲だが、屈折力が強い。
- 軸性近視:屈折力は正常だが、眼軸長が長い。
また、性状別で
- 単純近視:矯正視力良好で、屈折異常以外に視機能や眼底病変などを認めない。
- 病的近視:矯正視力不良で、その他の視機能及び眼底変性病変を認める。5歳以下では-4.00D、6~8歳では-6.00D、9歳以上では-8.00Dを超える近視とされている。
に分類できる。また、近視の程度によって、
- 弱度近視:≦-3D
- 中等度近視:-3D~-6D
- 強度近視:-6D~ー10D
- (最強度近視:-10D≦)
近視の診断
屈折検査の自覚検査には雲霧法によるレンズ交換法、赤緑テストがあり、他覚検査にはレフラクトメータ、検影器、フォトレフラクタを用いる。
近視の中には近視のように見える状態があります。水晶体の厚みを調節する毛様体筋という筋肉が過度に緊張した状態で、水晶体が厚くなることで網膜より前に焦点を結びます。これを偽(仮性)近視と言います。
仮性近視の原因としては長い時間近くの物を見続けた後、神経疾患、薬物、外斜視などが知られています。
小児近視患者の年齢別の近視の進行量
近視の進行が早いとされるのは、1年で0.75D以上の近視の進行で、中程度は1年で0.25D~0.75D程度である。
近視の治療
日常生活に不自由があれば、眼鏡およびコンタクトレンズを装用する。その他の矯正にはエキシマレーザーによる屈折矯正手術や眼内レンズによる外科的治療も可能でる。病的近視の合併症にはそれぞれに対する治療を行う。
1.デフォーカス組み込みレンズ
A.DIMS(Defocus Incorporated Multiple Segments)レンズ
2017年のWallineらの報告によれば、平均52%の近視進行抑制効果、平均62%の眼軸長伸展抑制効果、対象の学童近視の21.5%が進行停止するとされる。その後の研究結果では、DIMSレンズは副作用なく6年間にわたって持続的な効果を発揮することが示された。これら結果を踏まえて実際に、香港と中国本土ではすでに市販されている。一時的に周辺部のぼやけを認めることがあるが、ほとんどの症例で問題なく装用できている。リバウンド現象は確認されていない。
Long-term myopia control effect and safety in children wearing DIMS spectacle lenses for 6 years
I. HALT(Highly aspherical lenslets target)レンズ
DIMSレンズと類似のコンセプトで、中心部は単焦点レンズであるが、周辺部に高度な非球面性をもつレンズレットが同心円状に複数のリングとして配置されている。周辺部網膜の前に生じる近視性ボケの容積を広げる効果がある。8-13歳の中国人の子供に対する2年間の臨床研究では、HALTレンズは単焦点レンズよりも近視を遅らせるのに有効であることが示された。
Ⅱ. DOT(Diffusion optics technology)レンズ
中心部が単焦点レンズで、周辺部に拡散板を配置している。入射光を拡散板で軽度に散乱させることで、網膜像のコントラストをわずかに低下させることで近視を抑制するコンセプトのレンズ。1年間の臨床研究では、DOTレンズは対照レンズと比較して、1年間で近視の進行を74%抑制し、眼軸長の伸長を50%遅らせたと報告されている。
Ⅲ. その他
- CARE(Cylindrical Annular Refractive Element)レンズ:レンズ周辺部に同心円状に細い円柱レンズが多数配置された構造になっている。周辺部網膜に高次収差によるボケを作るコンセプトのレンズである。
B.DISC(Defocus incorporated soft contact)レンズ
DISCは3年間の抑制効果は屈折度が平均59%、眼軸長が平均52%であった。これもアメリカと日本を除く多くの国々で、近視進行抑制コンタクトレンズとして市販されている。
2.オルソケラトロジー

3.0.01%アトロピン点眼
近視進行抑制効果
ATOM1 studyでは1%アトロピン点眼による近視抑制効果のエビデンスが確立された。しかし、1%アトロピン点眼を中止した状態で1年間経過観察をしたところ、中止した眼は急激に近視が進行し、眼軸長が延長した(これをリバウンド現象という)。とはいえ、研究開始から3年経過後の時点でもコントロール群(偽薬投与群)と比較すれば近視進行は抑制されていた。
Atropine for the treatment of childhood myopia
このアトロピンのリバウンド対策として、より低濃度での効果を確かめる研究が行われた。それがATOM2 studyであり、このATOM2 studyでは0.5%、0.1%、0.01%に希釈して1日1回2年間点眼して近視進行を観察した。
ATOM2 studyでは濃度が0.01%であっても近視は抑制されており、点眼を中止しても0.5%、0.1%ではリバウンド現象は起きたが、0.01%では認められなかった。2年間で60%の抑制効果が示された。ただし、この報告では途中中止期間があることコントロール群がないこと、眼軸長については述べられていない点について注意が必要である。
ATOM-J studyではATOM2 studyと同様、0.01%アトロピンを用いて検討しており、2年間で18%の抑制効果と芳しくない結果であった。リバウンドは生じなかった。サブグループ解析では、瞳孔径の小さい症例で特に有効性が高く、瞳孔径が大きく調節をあまり使わずに近業作業をしている症例では効果の少ない可能性が示唆されている。
香港のLAMP Studyでは0.05%、0.025%、0.01%アトロピン点眼で検討しているが、偽薬と比較すると0.05%、0.025%、0.01%の近視進行は抑制されて、その効果は濃度依存性であった。この研究は2年目からは偽薬群が0.05%点眼に変わることが特徴的であり、その群は0.01%アトロピン群とほぼ同等の近視進行であった。このことから、0.05%アトロピンは0.01%の2倍の効果があると推測され、副作用と近視進行抑制の観点から0.05%が最も有効な濃度であると結論付けている。
近視の経過観察
- 近視の進行評価:1年に0.5D以上進行した場合を進行とする場合、6カ月で0.5D以上の進行があれば、何らかの治療を検討する必要がある。
- 眼軸長は小学生であれば年間平均0.3㎜程度の伸長があるため、6カ月であれば0.15㎜以上の伸長を近視進行ととらえるといった考え方もある。
- リバウンド現象を考えると15歳まで継続できると安心である。
近視発症予防
+1.0D~0D、片親が中等度以上の近視の4-9歳の児童について、0.05%、0.01%およびプラセボ群に分けて2年間経過観察。25%の症例で点眼後の不快感や来院困難を理由に脱落した。0.01%では効果がなく、0.05%では発症予防効果を認めている。
アトロピン点眼の課題
- 無効例が一定数存在し、ATOM1によれば1%アトロピンをしても2年間で1D以上の近視が進行した症例が13.9%存在していた。
- ATOM2では0.01%点眼をしても、近見障害や羞明で調光レンズを処方した例が6%存在した。
- 0.01% では3~5%程度、0.025%では10~20%の頻度で羞明を自覚する。
- 学童への長期投与の安全性もデータがまだ不十分である。
アトロピンの基礎
アトロピンはムスカリン受容体阻害薬である。ムスカリン受容体は副交感神経の神終末に存在し、副交感神経を制御している。よって、アトロピンはこのムスカリン受容体を競合阻害するため、散瞳、調節麻痺、心拍数の増加などを引き起こす。
散瞳効果は30~40分で最大となり、12日間程度継続する。調整麻痺効果は2~3時間で最大を示し、2週間程度継続するとされている。この効果は虹彩色素が多い目では効果の発現がさらに遅く、効果の消失にも時間がかかる。
4.0.01%アトロピン点眼+オルソケラトロジー併用

5.多焦点眼鏡
A.累進屈折力眼鏡(PAL)
PALは中心から下方へプラス度数が加入されている。PALを用いると、近見加入度数だけ調節必要量が減る。ただし、2011年のシステマティックレビューによれば、PALによる近視抑制効果は統計学的有意だが、効果自体が小さいため、臨床的な治療法としては推奨できないと結論づけられている。
B.Radial refractive gradient (RRG)レンズ
周辺網膜における後方デフォーカスえの対策として設計された。RRGレンズではほぼ同心円状に、中心から離れるに従って徐々にプラス度数が加入されている。
これを装用すると、少なくとも正面視の時は、周辺視野からくる光線はプラス度数加入領域を通るため、焦点が前方に移動し、周辺網膜における後方デフォーカスを軽減できる。ところが、期待に反して、屈折度と眼軸長いずれも抑制効果はなかった。
C.Positively-aspherized PAL(PA-PAL)
PA-PALはPALとRRGレンズのハイブリッドであるが、得られた2年間の近視進行抑制効果は平均20%程度であり、PALの抑制効果と大差なかった。
6.多焦点ソフトコンタクトレンズ(MSCL)
RRGレンズと同様、周辺視野から入社する光線がレンズ周辺部のプラス加入度数の領域を通過するため、周辺網膜における後方デフォーカスを軽減できると考えられた。さらに、コンタクトレンズはメガネに比べて、装用中のコンプライアンスが高いと考えられる。
単純なソフトコンタクトレンズと比較したRCTによれば、屈折度と眼軸長における抑制効果は、それぞれ平均26~77%と25~79%であった。ただし、MSCLのデザインのデザインが異なるため、今後の報告が待たれる。
MiSight 1 day
- 世界30か国以上の国々でMCSCLとして承認を受けて販売
- 素材は高含水ハイドロゲル
- 治療開始年齢:8-12歳
- 等価球面値-0.75D~-4.00D、乱視度数0.75D以下
メカニズム
- 中心に遠用度数、周辺に向かって+2.00D加入と交互に配置された二重焦点レンズ
- 加入部分が作り出す軸上および軸外の近視性収差により、眼軸伸長が抑制されると考えられている
近視抑制効果
- 治験は3部構成で、同素材の単焦点SCL(Proclear1day)と比較。
- Part1:3年間で眼軸長で52%、屈折で59%の近視抑制効果が示された。MiSight装用者の41%においては、この2年間に近視の進行は-0.25D以下であった(=ほとんど進行しなかった)。装用開始年齢にかかわらず約50%の近視抑制効果を確認(=開始が少し遅くなっても開始する価値はある)。
- Part2:3年間持続効果を調べている期間。MiSight群では引き続き抑制効果を維持。MiSightに切り替えられたコントロール群も同様の抑制効果を得られている。
リバウンド
- Part3:両群ともに単焦点SCLに切り替えたが、近視進行速度は治療開始前に戻っただけで、リバウンド現象は認めなかった。
A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control
Modelling Age Effects of Myopia Progression for the MiSight 1 day Clinical Trial
併用療法
- MiSightと低濃度アトロピン点眼の併用療法
- 2022年のイスラエルの後ろ向き研究:白人の近視のある6-15歳が対象。0.01%アトロピン点眼単独治療群(矯正はメガネ)vsMiSight+0.01%アトロピン点眼併用群。有意差なし。ただし、屈折値蚤の評価で、眼軸での検討はなし。
- 2024年の韓国の報告:近視のある7-13歳が対象。0.05%アトロピン点眼単独治療群vsMiSight+0.05%アトロピン点眼併用群。0.05%点眼の治療を行っても0.75D/年を超える近視進行または0.25㎜/念を超える眼軸長の増加を認める急速近視進行例に対し、MiSightを追加処方している。この併用群では、追加後に近視進行と眼軸長の伸びは有意に遅くなり、0.05%アトロピン点眼単独治療を続けた非急速近視進行群の進行速度と同等になった。特に、併用療法における眼軸伸長の抑制は、高度近視群より軽度および中等度近視群で顕著であった。
副作用
- 単焦点SCL群と満足度に差はない。
- ゴースト、ハロー・グレアについても90%以上が気にならないと回答している。
SEED 1day
- SEED 1dayPure EDOFはEDOFの多焦点SCLで、日本でも老眼用SCLとして2019年末より販売。
- 近視進行抑制はMiddleタイプというレンズで、治療開始時の年齢は6-12歳、等価球面値-0.75~-6.00D、乱視度数-1.00D以下を対象としている。制作範囲は-12.00Dまで。
メカニズム
- Retinal image quality(RIQ)を網膜後方で低下するように設計されているため、眼球の成長が促進されにくくなるとされる。
近視抑制効果
- 単焦点SCLとの2年間の比較では、眼軸長は30%程度の近視抑制効果が示されている。
- 2022年のWengらの報告では、MiSightと同様の効果が示されている。
リバウンド
- リバウンドに関する報告はまだない。
併用療法
- 低濃度アトロピン点眼の併用効果に関する報告はまだない。
副作用
- EDOF SCLの網膜像のピークはやや近視寄りで、-0.25D~-0.75D程度(瞳孔径による)、近視側によっているため、それを踏まえて処方をする。
- 乱視には対応していないため、1.00Dを超える乱視症例では見え方の満足を得ることが難しい場合がある。
レッドライト治療
赤色光(650 nm、1600 lux、3 min × 2/day)を用いる方法であり、非常に強い近視進行(眼軸長伸長)抑制効果が確認されています。メカニズムは完全には明らかではないですが、脈絡膜が肥厚化することが分かっています。また、前近視に対する近視発症抑制効果も報告されていますが、安全性などは未解決の部分もあります。
- 2008年に光治療機器が弱視治療用として認可された。
- 2012年に弱視治療に対する光治療の有効性が報告された。
- 2014年に本機器で用いた赤色光の近視に対する有効性が見つかった。
- 2024年現在、30カ国以上で医療機器して認可され、全世界ですでに15万人以上の小児に使用されている。
Low-level laser therapy improves visual acuity in adolescent and adult patients with amblyopia
近視進行抑制効果
- 8-13歳の-1.00~-5.00Dの中国人小児264人を、レッドライト治療群と単焦点眼鏡群に割り当てた比較試験で、1年後単焦点眼鏡群の眼軸伸長量は0.38㎜で、レッドライト治療群では0.13㎜であった。
- 単焦点眼鏡群の近視進行量は-0.79Dであったのに対し、レッドライト治療群では-0.20Dであった。
- レッドライト治療の近視抑制効果がは単焦点眼鏡群と比較して、眼軸長で69.4%、近視度数で76.6%。
- 75%以上のコンプライアンス良好群のみを抽出した場合、近視抑制効果は眼軸長で76.8%、近視度数で87.7%。
- また、レッドライト治療群では12か月間の治療後に0.05㎜以上の眼軸長の短縮が21.6%の患児で観察された。
- 同グループは1年間の比較試験の続報として、2年目のフォローアップ研究を2022年に報告した。
Orthokeratology and Low-Intensity Laser Therapy for Slowing the Progression of Myopia in Children
- レッドライト2年継続群は単焦点眼鏡群2年継続群と比較して、近視進行抑制効果は眼軸長、近視度数ともに75%であった。
- 眼軸長抑制率は1年目が84.5%、2年目が63.0%(初年度の方が抑制効果が高い)。
- リバウンド:1年目でレッドライト治療を中断した群では、2年継続群より早いリバウンド、リバウンドの程度は単焦点眼鏡群2年目の進行速度と同程度のため中程度。
副作用
- 羞明
- 閃光盲
- 残像
- 網膜障害と視力低下(→治療中断で回復)
Retinal Damage After Repeated Low-level Red-Light Laser Exposure
レッドライト治療の出力と近視抑制効果
- 出力は0.35~2.0mW
- 2024年に6-15歳の近視の中国人小児200人を対象にした報告では、0.37mW、0.60mw、1.20mWの出力間で平均屈折度数変化量、平均眼軸長伸展量に有意差はないが、より高い出力の方が効果的であることが示唆された。
Efficacy of Different Powers of Low-Level Red Light in Children for Myopia Control
レッドライト治療とオルソケラトロジーの相加効果
- レッドライト治療は低濃度アトロピン点眼との併用は禁忌
- オルソケラトロジー治療を行っても、年間0.50㎜以上の眼軸長伸展があった8-13歳の近視(-1.00D~-5.00D)に対して、1年間オルソケラトロジーを継続する群と、レッドライト治療を併用する群に分けたところ、オルソケラトロジー単独群で0.27mm/年、レッドライト治療併用群ではー0.02mm/年であった。
近視性不同視
定義と有病率
- 国際的には等価球面度数の差が左右で1.0D以上、日本では2.0D以上の差を不同視とする。
- アメリカにおける6か月、5歳、12~15歳の計1827人の非調節麻痺下屈折値での不同視の有病率:1.96%、1.27%、5.77%であった。
Anisometropia in children from infancy to 15 years
- 日本における小学生350人を対象とした5年間の縦断研究では、球面度数差が1.00D以上の有病率は6歳で1.43%、11歳で3.14%に増加した。
- 乱視性不同視の有病率も6歳児の2.6%から11歳時の4.3%へと増加した。
- シンガポールにおける7-9歳の不同視の有病率は3年間の追跡期間中に3.6%→9.9%に増加し、近視小児の方が不同視の有病率が有意に高かった。
不同視の進行パターン
- COMET研究:6-12歳のアメリカ人を対象にした研究で、13年間追跡したところ、89%でSEの変化率は両眼で同じであったが、11%で不同視となった。
- 不同視の有病率と進行量は全体として経時的にぞうかするが、不同視の大きさについては13年間で0.24Dから0.49Dであった。
- より強い近視進行がみられた群は、そうでない群と比較して、不同視および軸性不同視の有意な変化量を示す可能性が高かった。
- BAM(bilateral anisometropic myopia:両眼性近視性不同視、両眼とも近視)、UAM(unilateral anisometropic myopia:片眼性近視性不同視、片眼は近視、他眼は遠視or正視)
- 6-16歳のインド人小児を対象とした後ろ向き研究で、BAMとUAMでは不同視の両眼差の進行が異なり、不同視のない両眼近視眼の1年間の近視進行量はー0.49±0.54D/年、BAMでは近視が強い方の眼の近視進行量は-0.45±0.55D/年、近視度数が小さい方の眼は-0.37±0.55D/年であったのに対し、UAMあでは-0.39±0.51D/年で、正視眼の-0.22±0.36D/年と比較して有意に大きかった。3年間の結果にするとより顕著となる。
Progression pattern of non-amblyopic Anisomyopic eyes compared to Isomyopic eyes
メガネによる不同視の変化
- 不同視をメガネで矯正すると、像の大きさの左右差を感じるため、不等像視が出る可能性があるため、不同視はメガネよりもCLによる治療の方が良いとされる。
- UAMの子どもはメガネ装用を拒否される場合があるが、正視眼と比べ近視眼の近視進行が顕著であることもある。8-12歳において未矯正UMAと矯正UMAを比較すると、近視眼におけるSEおよびALの変化量は、矯正群では正視眼と近視眼で有意差はなかったが、未矯正群では有意差があった。また、サブグループ解析で、矯正後にSEとALが大きくなったことも示されている。
低濃度アトロピン点眼による不同視治療
- 近視性不同視患児に、近視度の大きい眼に対して1%アトロピン点眼を3日に1回使用すると、両眼間の差が治療開始時の1.82±0.73Dから9か月後には0.47D±0.65Dへと減少していた。ただし、リバウンド現象の観点から臨床応用はされていない。
Treatment outcomes of myopic anisometropia with 1% atropine: a pilot study
- メガネに加えて0.01%あるいは0.05%アトロピン点眼を使用した報告もあるが、0.05%アトロピン点眼群では、ALの両眼間の差はわずかに減少したが、0.01%アトロピン点眼群ではほぼ変化していなかった。
オルソケラトロジーによる不同視治療
UAMに対する有効性
- 8-15歳25名を対象にした後ろ向き研究:治療眼の1年後のAL伸長量は未治療眼よりも有意に抑制。しかし、1年の経過で64%が未治療眼に近視を発症した。また、平均15.5カ月の追跡調査後にUAM患者の32%がBAMを発症していた。そして、新たに近視になった眼に対しても、オルソケラトロジーの治療でAL伸長が有意に遅くなったとしている。
Effects of orthokeratology on axial length growth in myopic anisometropes
- 31名の2年間の後ろ向き研究:ALの両眼間の差はベースラインと比較して、2年後には著しく減少していた。
- 1年間の追跡調査で、UAMの48.1%がBAMを発症していた。
BAMに対する有効性
- 102名をオルソケラトロジー群とメガネ群に割り当て、1年の経過を観察した前向き介入研究(中国):オルソケラトロジー群において近視度の大きい眼のAL伸長量は近視度の小さい眼の伸長量と比べて有意に少なくなり、1年間の治療によってALの両眼間の差は有意に減少した。メガネ群ではAL伸長量は両眼でほぼ同等で、1年間の治療でALの眼間差に有意な減少あh認められなかった。
- BAMの両眼にオルソケラトロジ、0.01%アトロピン点眼、0.05%アトロピン点眼で治療した後ろ向き研究では、オルソケラトロジー群において0.01%アトロピン点眼群や0.05%アトロピン点眼群と比較して、2年後のALの両眼間の差が有意に減少していることが分かった。
近視抑制治療の評価法
- 国際近視機関(IMI)は診断はサイプレジ調節麻痺下屈折検査による屈折検査で実施し、近視進行のモニターは屈折検査と眼軸長計測結果を用いることを推奨している。
IMI – Clinical Myopia Control Trials and Instrumentation Report
- 眼軸長は屈折度を形成する要素の一つであるため、眼軸長単独ではなく、角膜曲率版権を組み合わせたAL/CRC>2.9~3.1による定義を用いる方がより正確に近視を診断できる。
- ただし、屈折検査は再現性が低いが、非接触型の光学的眼軸長計測は再現性が高い。
- 成人の場合眼軸長1㎜の伸展は屈折度数に換算すると3.0Dもしくは2.7Dに相当するが、小児では水晶体や角膜屈折力が弱まることで代償が生じるため、年間1㎜の眼軸長伸展は屈折度数に換算して0.45Dの変化に相当することに注意する。
- 日本人小児のデータを用いた管理表:Axial Manager (トーメーコーポレーション、OA-2000に搭載可能)、Myopia Master(Oculus社のレフラクトメータ、GRAS搭載で、軸性近視と屈折性近視が鑑別可能)
病的近視
2015年の国際メタ解析研究によって、病的近視に伴う様々な種類の眼底病変は近視性黄斑症と総称され、近視性網脈絡膜萎縮病変と、いかなる段階の近視性網脈絡膜萎縮病変に生じうる3つの独立病変(lacquer cracks、近視性CNV、Fuchs斑)から構成されることが定められた。
これを基にして病的近視は「びまん性萎縮以上の近視性網脈絡膜萎縮病変もしくは独立病変を認めるもの、または後部ぶどう腫を有する眼」と定義された。その他にも、近視性牽引黄斑症、近視性緑内障様視神経症がある。
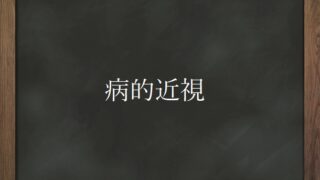
参考文献
- 今日の眼疾患治療指針第3版
- 第74回日本臨床眼科学会シンポジウム6強度近視による失明予防に向けて
- あたらしい眼科Vol.37,No.5,2020
- あたらしい眼科Vol.37,No.12,2020
- あたらしい眼科Vol.42,No.2,2025
- Long-term myopia control effect and safety in children wearing DIMS spectacle lenses for 6 years
- Spectacle Lenses With Aspherical Lenslets for Myopia Control vs Single-Vision Spectacle Lenses: A Randomized Clinical Trial
- Control of myopia using diffusion optics spectacle lenses: 12-month results of a randomised controlled, efficacy and safety study (CYPRESS)
- Three-Year Clinical Trial of Low-Concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) Study: Continued Versus Washout: Phase 3 Report
- Efficacy and safety of 0.01% atropine for prevention of childhood myopia in a 2-year randomized placebo-controlled study
- Assessment of myopic rebound effect after discontinuation of treatment with 0.01% atropine eye drops in Japanese school-age children
- Five-Year Clinical Trial on Atropine for the Treatment of Myopia 2: Myopia Control with Atropine 0.01% Eyedrops
- Atropine for the treatment of childhood myopia
- Effect of Low-Concentration Atropine Eyedrops vs Placebo on Myopia Incidence in Children: The LAMP2 Randomized Clinical Trial
- Myopia control with novel central and peripheral plus contact lenses and extended depth of focus contact lenses: 2 year results from a randomised clinical trial
- Efficacy of contact lenses for myopia control: Insights from a randomised, contralateral study design
- Low-level laser therapy improves visual acuity in adolescent and adult patients with amblyopia
- Orthokeratology and Low-Intensity Laser Therapy for Slowing the Progression of Myopia in Children
- Effect of Repeated Low-Level Red-Light Therapy for Myopia Control in Children: A Multicenter Randomized Controlled Trial
- Retinal Damage After Repeated Low-level Red-Light Laser Exposure
- Efficacy of Different Powers of Low-Level Red Light in Children for Myopia Control
- Myopia Control Effect of Repeated Low-Level Red-Light Therapy Combined with Orthokeratology: A Multicenter Randomized Controlled Trial
- Anisometropia in children from infancy to 15 years
- A longitudinal study of cycloplegic refraction in a cohort of 350 Japanese schoolchildren. Anisometropia
- Limited change in anisometropia and aniso-axial length over 13 years in myopic children enrolled in the Correction of Myopia Evaluation Trial
- Spectacle correction may affect refractive progression in children with unilateral myopic anisometropia: A retrospective study
- Treatment outcomes of myopic anisometropia with 1% atropine: a pilot study
- A comparative study of orthokeratology and low-dose atropine for the treatment of anisomyopia in children
- Effects of orthokeratology on axial length growth in myopic anisometropes
- Assessing the change of anisometropia in unilateral myopic children receiving monocular orthokeratology treatment
- Effects of orthokeratology lens on axial length elongation in unilateral myopia and bilateral myopia with anisometropia children
- Relative corneal refractive power shift and inter-eye differential axial growth in children with myopic anisometropia treated with bilateral orthokeratology
- IMI – Clinical Myopia Control Trials and Instrumentation Report
- Significant Axial Elongation with Minimal Change in Refraction in 3- to 6-Year-Old Chinese Preschoolers: The Shenzhen Kindergarten Eye Study
- The Relationship between Progression in Axial Length/Corneal Radius of Curvature Ratio and Spherical Equivalent Refractive Error in Myopia
関連記事