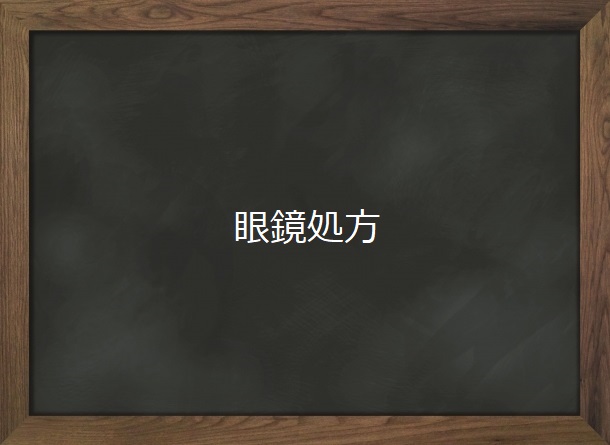スポンサーリンク
もくじ
眼鏡処方
自覚的屈折検査および他覚的屈折検査で求めだ屈折度を基に、生活習慣などを考慮して、眼鏡処方箋を作成する。検眼レンズは市販のレンズとデザインが異なったり、短時間での使用に限られる。そのため、眼鏡作製後に眼鏡が合わないこともありうる。
眼鏡処方の課題
1.不等像視の問題と対策
眼鏡のレンズは角膜頂点から通常12㎜前方に置かれているため、倍率効果が見られる。
不同視を完全矯正しようとすると、眼鏡のレンズを通しているイメージの左右差(不等像視)により、眼精疲労や眼痛、複視などの症状が起こる。ただし、小児では感覚的順応により、完全矯正できる場合が多い。
球面レンズでは不等像の許容範囲は6~8%とされるが、球面度数の左右差が1.5Dを超えないことが望ましいとされる。また、円柱レンズでは経線不等像視による異常空間感覚が起こる場合がある。
2.眼鏡処方における焦点深度の考え方
焦点深度は瞳孔径、眼軸長、収差、潜在的視力等の様々な因子の影響を受ける。特に老眼、眼内レンズ挿入眼などでは、焦点深度を考慮して眼鏡処方をすることによって、明視域の増大や眼鏡装用感が改善する。
具体的には、老眼に対して累進屈折力レンズで眼鏡処方をする場合、遠用部にわずかな近視を残すと、近見加入度数の軽減によって装用感が改善する。また、単焦点眼内レンズ挿入眼に対して、軽度近視性乱視を残すことで、裸眼での明視域は広くなる。
焦点深度は視力低下例ほど大きくなる傾向にある。そのため、ロービジョン患者では、遠見視力が低下しない程度に近視を矯正すると、健常者より広い明視域を確保することができる。
参考文献
関連記事
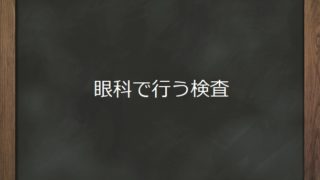
眼科で行う検査このページでは眼科で行う検査に関する記事のリンクを掲載しています。...