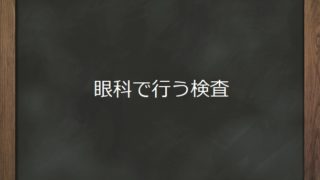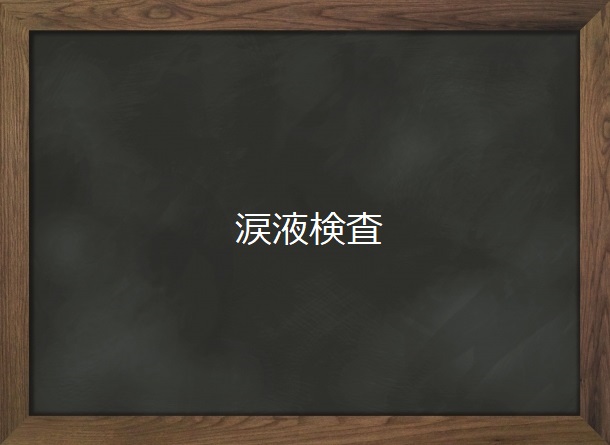と疑問をお持ちの方の悩みを解決できる記事になっています。
涙液検査はドライアイのスクリーニング検査(ドライアイの有無や程度の検査)で行うことが多い。
もくじ
涙液検査とは
涙液検査は涙液の異常を調べる検査で、量と質の面から評価する。
1.涙液の量を調べる検査
涙液検査では大きく2つ量を観察する。
- 涙液貯留量:涙液基礎分泌に関係している。眼表面で利用されている涙液量のこと。
- 反射性涙液分泌量:眼表面に異常が生じたときにそれを回復に向かわせる指標となる涙液量のこと。
2.涙液の質を調べる検査
涙液の実際の中身を調べる検査はなく、涙液の性質を調べるため涙液層の安定性を検査する。
涙液検査の原理と特徴
1.涙液の量を調べる検査
A. 涙液貯留量を調べる検査
涙液メニスカスは下の写真で黄緑色に染まった一帯を指す。

mivisionHPより引用
涙液メニスカスには眼表面全体の涙液量の75~90%が貯まり、下眼瞼中央の涙液メニスカスの”高さ”や”曲率半径”は、眼表面全体の涙液量と相関する。
そのため、涙液メニスカスはドライアイと正常眼とを区別する指標として用いられる。一般的には、涙液メニスカスの中央部の高さを用いるが、細隙灯顕微鏡にマイクロメータを取り付けての計測は容易ではない。
最近は、涙液メニスカスの高さを計測するため、前眼部OCTが用いられるようになった。一方、曲率半径はメニスコメトリ法を用いて計測するが、通常行われることはないため、ここでは下記に補足として記載する。
メニスコメトリ法
メニスコメトリとは、涙液メニスカスの曲率半径を非侵襲的に計測する方法で、眼表面の涙液貯留量の評価法の1つである。
曲率半径は涙液貯留量に比例するため、点眼液使用後の曲率半径の経時変化を調べると、点眼液の滞留性(貯まりやすさ)や導涙系の疎通性(鼻への流れやすさ)を評価することができる。
ビデオメニスコメータでは、涙液メニスカスの表面に水平線を投影し、メニスカスにおける小さな鏡面反射像を拡大してビデオ収録する。そのデータを画像解析し、曲率半径を求める。
しかし、結膜弛緩症や眼位のズレがあると、曲率半径を正確に計測することができない。曲率半径が得られ、その値が0.25㎜以下であれば涙液減少型ドライアイを疑う。
![Diagram of meniscometry, edited image of [6]. | Download Scientific Diagram](https://www.researchgate.net/publication/321925517/figure/fig1/AS:573441527828480@1513730522718/Diagram-of-meniscometry-edited-image-of-6_Q320.jpg)
Research Gate HPより引用
B. 反射性涙液分泌量を調べる検査
反射性涙液分泌量の評価はSchirmer(シルマー)テスト1法が最も一般的である。

Research Gateより引用
Schirmer試験紙(5×35㎜)が結膜表面を刺激し、自然な瞬きで分泌される涙液量を測定できる。障害部位の診断や再現性が乏しいという欠点はあるが、ドライアイの有無を判断する際に重要な検査である。
Schirmer試験紙を使う際には、鼻上側を見てもらい、上図のように下眼瞼の外側1/3の部位にSchirmer試験をかける。
2.涙液の質を調べる検査
涙液の質を調べるためには涙液層の安定性を評価することが多い。その涙液層の安定性は涙液層破壊時間(BUT)によって評価される。
BUTの測定方法
- フルオレセインで涙液を染める。
- 瞬きしてもらう。
- 閉瞼してもらい、その後開瞼を維持してもらう。
- dark spot(蛍光がなくなり暗くなった領域)が出てくるまでの時間を計測する。
- 正式には3回行い、その時間の平均値を求める。
その他にも、インターフェロメトリやトポグラフィの原理を応用した方法(TSAS)などもあるが、一般的ではないため割愛する。
涙液検査を行う際の注意点と判定
涙液検査は互いの検査結果に影響を及ぼすため、
- 涙液メニスカスを観察する
- BUTを測定する
- 10分間空ける(←反射性に増加した涙液量をベースラインに戻すため)
- Schirmerテスト1法を行う
以上の順で試験を行い、得られた結果からドライアイの有無などを判定する。
正常値は下記の通りである。
- 涙液メニスカス:0.1~0.3㎜が正常
- BUT:5秒以下が異常
- Schirmer1法:5分値で5㎜以下が異常
参考文献
関連記事