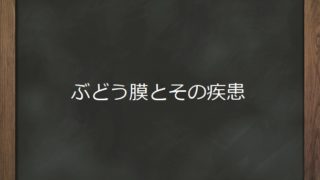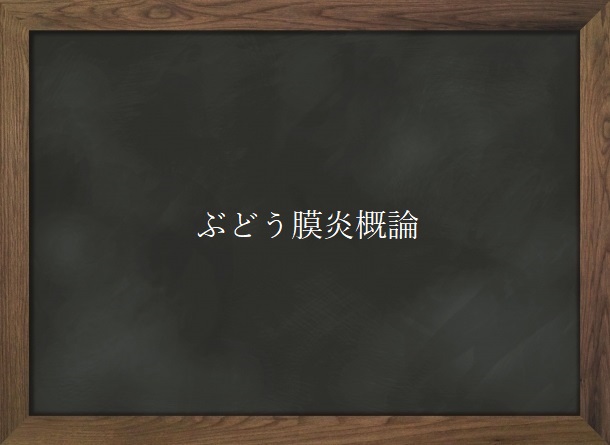もくじ
ぶどう膜炎とは
ぶどう膜(虹彩、毛様体、脈絡膜)に炎症が起きた状態で、部位によって前部ぶどう膜炎、中間部ぶどう膜炎、汎ぶどう膜炎に分けられる。あるいは、組織名で虹彩炎、虹彩毛様体炎、脈絡膜炎、網脈絡膜炎に分けられる。その他にも、感染が内因性か外因性か、肉芽腫性か非肉芽腫性かなどで分ける。
ぶどう膜炎の特徴
1.疫学
2016年に実施された全国疫学調査では、全年齢層でのぶどう膜炎の原因疾患は、サルコイドーシス(10.6%)、Vogt-小柳-原田病(VKH)(8.1%)、ヘルペス性前部ぶどう膜炎(6.5%)、急性前部ぶどう膜炎(5.5%)、強膜炎ぶどう膜炎(4.4%)、Behcet病(4.2%)が上位を占めている。
- ベーチェット病:20-30歳代に多い。
- サルコイドーシス:若年者、高齢者の2峰性。
- 若年性特発性関節炎を含む若年性虹彩毛様体炎:小児に多い。
- 男性に多い:ベーチェット病
- 女性に多い:若年性特発性関節炎を含む若年性虹彩毛様体炎、50歳以上のサルコイドーシス
- 九州、四国に多い:HTLV-1関連ぶどう膜炎
- 日本に多い:サルコイドーシス、ベーチェット病
- 白人に多い:多発性硬化症に伴うぶどう膜炎、HLA-B27関連ぶどう膜炎
- 猫、鳥などの飼育歴、豚肉などの生食:トキソプラズマ症
※高齢者ではサルコイドーシス、ヘルペス性疾患、眼内悪性リンパ腫、VKH、真菌性眼内炎の頻度が高い。そのため、高齢者を診察する際には、一般的に割合の多いサルコイドーシスやVKHに加えて、ヘルペス性前部ぶどう膜炎、眼内悪性リンパ腫、感染性の後部ぶどう膜炎は常に意識する必要がある。
2.診察所見
A. 疾患別
- 原田病:近視化(毛様体浮腫、水晶体前方偏位)も遠視化(漿液性網膜剥離)も起こりうる。毛様体浮腫による浅前房。
- 若年性特発性関節炎を含む若年性虹彩毛様体炎:帯状角膜変性
- Posner-Schlossman症候群:患眼で隅角色素減少。虹彩萎縮。Koeppe結節を認めることもある。
- Fuchs虹彩異色虹彩毛様体炎:虹彩萎縮による異色。Koeppe結節を認めることもある。虹彩後癒着はない。
- ぶどう膜炎:白内障(特に後嚢下白内障)
B. 所見別
- 豚脂様角膜後面沈着物:サルコイドーシス、結核性ぶどう膜炎、間質性腎炎関連ぶどう膜炎(TINU)、ヘルペスウイルス虹彩毛様体炎、急性網膜壊死など
- サラサラした(体位変換で移動する)ニボーを伴う前房蓄膿:ベーチェット病
- 粘稠性の(体位変換で移動しない)前房蓄膿:HLA-B27関連ぶどう膜炎、強直性脊椎炎、炎症性腸疾患に伴うぶどう膜炎
- 扇状の虹彩萎縮・麻痺性散瞳:ヘルペスウイルス虹彩毛様体炎
- 虹彩、隅角ルベオーシス:ベーチェット病、若年性特発性関節炎を含む若年性虹彩毛様体炎
- 網膜静脈炎:サルコイドーシス、結核性ぶどう膜炎、眼トキソプラズマ症
- 網膜動脈炎:結核性ぶどう膜炎、眼トキソプラズマ症
- 動脈の白鞘化:急性網膜壊死
- 視神経腫脹に伴う白色滲出斑(1週間前後で消失する):ベーチェット病
3.蛍光眼底造影検査
A. フルオレセイン蛍光眼底造影検査(FA)
- 病変部が初期に低蛍光、後期に過蛍光へと変化する逆転現象:APMPPE
- 病巣周囲の蛍光漏出:トキソプラズマ症
- 多発性点状蛍光漏出とそれに伴う蛍光貯留:原田病
B. インドシアニングリーン蛍光造影検査(IA)
- 原田病:dark spot
4.眼内サンプリング
- 前房水からのPCR法によるDNA検出:ヘルペスウイルス虹彩毛様体炎、急性網膜壊死
- Q値(血清中と前房水中の抗体価の比):眼トキソプラズマ症
- 悪性リンパ腫:硝子体液中のIL-10/IL-6比上昇
5.HLA抗原
- HLA-A26:ベーチェット病
- HLA-A29:散弾状網脈絡膜症
- HLA-B27:強直性脊椎炎、炎症性腸疾患、乾癬、Reiter病
- HLA-B51:ベーチェット病
- HLA-DR4:原田病
ぶどう膜炎の治療
ぶどう膜炎の原因が分かればその治療、そうでなければ対症療法を行う。
年齢に応じたステロイド治療の注意点
高齢者では若年者と比べて、脊椎圧迫骨折のリスクは26倍であり、内服開始から骨折までの期間が短かったという報告がある。
不可逆的な視機能障害をきたす恐れのある重篤な後眼部炎症およびGC局所治療に抵抗性を示す重篤な前眼部炎症を伴う非感染性小児ぶどう膜炎に対してグルココルチコイド(GC)の全身療法を行うが、GCの副作用を考慮して全体の投与期間として3か月程度を目安とする。
1.ステロイド点眼液
前眼部炎症に対して有効で、消炎とともに漸減する。
2.散瞳点眼薬
虹彩後癒着予防で用いる。
3.ステロイド局所注射
前眼部の炎症が強い場合は結膜下注射、後眼部の炎症が強い場合はTenon嚢下注射が有効とされる。
4.ステロイド薬全身投与
局所投与で効果不十分であれば全身投与を行うことがある。特に、原田病は消炎と免疫抑制効果を期待してステロイド大量投与またはステロイドパルス療法を行う。
5.その他の全身投与薬
ベーチェット病に対しては、眼発作予防のためコルヒチン、シクロスポリンを用いる。また、TNF阻害薬であるインフリキシマブなども用いる。
緑内障患者の継続受診率を初診時の緑内障年代別に検討した報告では、80歳以上では受診率が50%台と他の年代と比べて有意に低いことが示されている。
6.手術
A. 白内障手術
術後炎症を惹起する恐れがあるため、3カ月以上の無発作期間があることが望ましい。
B. 緑内障手術
点眼や内服で眼圧コントロールが難しければ手術が必要となる。虹彩後癒着から虹彩膨隆した場合は、レーザー虹彩切開術や周辺虹彩切除術を行う。
続発緑内障の手術成績
「手術の成功=術後眼圧が21未満かつ追加緑内障手術が不要であること」と定義した場合、45歳以上と45歳未満では45歳以上の群が手術成功率は有意に高いとされている。
Characteristics of uveitic glaucoma and evaluation of its surgical treatment
「手術成功=術後眼圧が15未満」と定義すると、log-rank testで有意差はないが、POAGと比して高い傾向があることが示されている。
TLE手術失敗例における危険因子につい調べた結果では、性別、年齢、肉芽腫性ぶどう膜炎、汎ぶどう膜炎、白内障手術併施、偽水晶体眼、術前眼圧、術後炎症増悪、白内障手術後の項目の中で、術後炎症増悪のみが有意な危険因子であることが示された。
360° suture trabeculotomy(S-LOT)についての手術後平均眼圧を調べ
た報告では、POAGと比較し術前眼圧が高いUGでも長期間にわたり低い眼圧を維持していることが示されている。
microhook trabeculotomyを行ったUG患者の術前後の眼圧を調査したところ、術前眼圧(中央値)30.5 mmHgから、術後12か月(中央値)では15 mmHgまで有意に低下しており、緑内障点眼数(中央値)も術前5から術後は2.5に減少できたことを報告している。
Outcomes of Microhook ab Interno Trabeculotomy in Consecutive 36 Eyes with Uveitic Glaucoma
PRESERFLO Microshuntを行ったUG患者の術後の平均眼圧は、ベースライン眼圧と比べて術後6か月では30.7%、術後12か月では26.5%、術後24か
月では33.5%、術後36か月後では30.1%有意に低下しており、平均緑内障点眼数も術前4.1から術後0.9まで減少できたことを報告している。
Preserflo microshunt implant for the treatment of refractory uveitic glaucoma: 36-month outcomes
80歳以下と81歳以上の緑内障患者に対するTLE術後成績を比較し、術後1年成績は両群に差はなく、術後合併症や再手術の有無、術後に要した点眼数についても有意差は認められなかったとされる。
Trabeculectomy in Patients With Glaucoma Over 80 Years of Age: Relatively Short-term Outcomes
C. 硝子体手術
悪性リンパ腫に対する硝子体生検、急性網膜壊死に対する網膜剥離に対して硝子体手術を施行する。
参考文献
- 眼科学第2版
- Clinical features of uveitis in elderly patients in central Tokyo (2013-2018)
- Uveitis and pseudouveitis presenting for the first time in Japanese elderly patients
- 小児非感染性ぶどう膜炎初期診療の手引き 2020年版
- Clinical practice. Glucocorticoid-induced bone disease
- 高齢者緑内障に対する選択的レーザー 線維柱帯形成術の使い方
関連記事