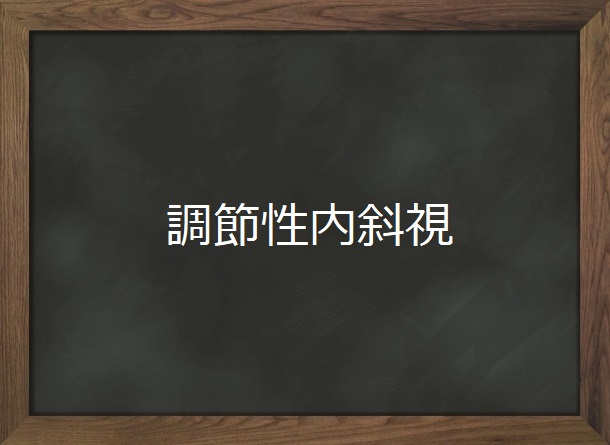もくじ
調節性内斜視とは
調節性内斜視は遠視があるために起こる内斜視である。遠視を打ち消すために調節を働かせ、それによる調節性輻輳が起こるため内斜視になる。
小児期の内斜視の中で最も頻度が高い(53%)。1.5~4歳に発症することが多い。診断には調節麻痺下の屈折検査が重要で、治療のメインは眼鏡装用とされる。調節性内斜視は下記のように分類できる。
- 屈折性調節性内斜視
- 部分調節性内斜視
- 非屈折性調節性内斜視
1.屈折性調節性内斜視
遠視の完全矯正眼鏡により斜視角が10Δ以上減少し、かつ遠見の残余斜視角が+10Δ未満となる調節性内斜視のこと。
2.部分調節性内斜視
遠視の完全矯正眼鏡により斜視角が10Δ以上減少し、かつ遠見の残余斜視角が+10Δ以上となる調節性内斜視のこと。
屈折性調節性内斜視に比べ、発症年齢が早く、初診時年齢も早く、また眼鏡装用前の初診時斜視角は部分調節性内斜視の方が大きいという報告がある。
3.非屈折性調節性内斜視
遠視と関係なく、近見時に内斜視角が増大する調節性内斜視のこと。調節性内斜視のうち15%程度が高AC/A比と言われる。近見時の内斜視は整容的問題、眼精疲労、両眼視機能の障害を起こす。
調節性内斜視の原因
- 屈折性調節性内斜視
:遠視により調節性輻輳が引き起こされた結果起こる。遠視度数は中等度(+2.0D~+8.0D程度)以上が多い。 - 非屈折性調節性内斜視
:高AC/A比(7~9Δ/D)により、近見時に内斜視角が増大する。 - 部分調節性内斜視
:1,2の原因が混合で起こる。
乳児調節性内斜視
1歳未満に発症する調節性内斜視で、+2D以上の遠視があり、発症時に斜視角が変動する。+2D以上の遠視がある場合は、調節性内斜視を疑い完全矯正眼鏡を処方する。3カ月間は眼位の改善が無いかを確認する。ただし、通常+4D未満の遠視で起こることは稀である。

調節性内斜視の症状
初発症状は間欠性の内斜視で、近くを見るといや疲れたときになりやすい。片眼弱視を合併することがある。
屈折性調節性内斜視の両眼視機能はおおむね良好で、部分調節性内斜視では良悪様々である。
乳児内斜視から移行したものは両眼視機能は不良で、屈折性調節性内斜視から移行したものは両眼視機能は比較的良好である。
調節性内斜視の診断
調節麻痺下の屈折検査(硫酸アトロピンの場合は1日2回7日間点眼)を行い、完全矯正眼鏡装用で、
- 遠見、近見ともに10Δ以上の内斜視角の減少がみられ、かつ残余斜視角が+10Δ未満に改善する。
→屈折性調節性内斜視 - 10Δ以上の内斜視角の減少がみられ、かつ残余斜視角が+10Δ以上
→部分調節性内斜視 - 遠視があっても軽度であるにもかかわらずAC/A比が高いため近見時に内斜視になる
→高AC/A比による非屈折性調節性内斜視
発症が1歳未満でも遠視が+2.0D以上なら、まず眼鏡装用させて斜視角の変化を観察し、乳児内斜視との鑑別を行う。
ただし、調節性内斜視かどうかの診断を下すまでには3カ月程度は経過観察する必要がある。
AC/A比は1D調節することで引き起こされる輻輳量(Δ)で、正常値は4±2(Δ/D)である。年齢によって減少する。
調節性内斜視の治療
調節性内斜視では完全矯正が望ましい。遠視を減らすことなく、乱視も増減せず処方する。
- 屈折性調節性内斜視
:遠視の完全矯正で正位となり、手術適応とならない。 - 部分調節性内斜視
:遠視の完全矯正眼鏡でも斜視が目立つ場合、または両眼視機能の向上が手術により期待できる場合は手術治療を選択する。ただし、遠視眼鏡装用下の斜視角に対してのみ行う。また、フレネル膜によるプリズム療法も有用とされる。弱視の合併がある場合は健眼遮閉で治療する。弱視治療は非調節成分の解消をサポートし、手術の必要性を減らす可能性があるため、手術より先に弱視治療を行う。ただし、健眼遮閉は両眼視機能や融像を妨げ、斜視を悪化させる可能性もあり、注意が必要である。 - 非屈折性調節性内斜視
:近見時に+3.0D を負荷した二重焦点眼鏡を処方する。見かけが気になる場合は累進屈折眼鏡を処方する。
眼鏡装用から内斜視角減少の期間は、ほとんどが眼鏡装用から3か月以内で眼位が落ち着く。
瞳孔間距離
内斜視では、両眼開放のまま瞳孔間距離を測定すると実際より短くなる。実際より短い瞳孔間距離の処方は内方基底のプリズム効果が出て、むしろ内斜視の眼位を増悪させることになる。そのため、正確な瞳孔間距離は片眼ずつカバーして測定する。
<日本人の平均瞳孔間距離>
2~3歳:48㎜
4~5歳:52~54㎜
6~7歳:53~54㎜
治療用眼鏡等作成指示書
9歳未満の調節性内斜視に対する眼鏡は保険適用で、5歳未満では前回の給付から1年以上、5歳以上では前回の給付から2年以上経過すれば再給付可能となる。
調節性内斜視の予後
屈折性調節性内斜視で、成長とともに遠視が減少し、最終的に眼鏡を装用しなくても正位となるものは全体の約15%ほどである。また、立体視が良好なものの特徴は遠見で≦4Δ、近見で≦5Δの眼位ずれ、発症から1年以内に治療を受けたもの、発症時期が遅いなどが挙げられる。
残りは屈折性調節性内斜視の状態が続いたり、部分調節性内斜視に移行する、あるいは外斜視に移行するなど様々である。
調節性内斜視は眼鏡装用開始から6~8週間後に解消すると言われている。一方で、調節性内斜視の1/3の症例では手術が必要になる。手術適応となるのは下記が挙げられる。
- 眼鏡にて残余斜視角が大きな部分調節性内斜視
- 非屈折性調節性内斜視のうち、二重焦点眼鏡を使いこなせず、近見眼位が不良な小児
- 青年期になってもAC/A比の正常化がみられず二重焦点眼鏡が注視できない
調節性内斜視の遠視度数は7歳までは同程度か増加し、それ以降減少すると言われている。適切な眼鏡を使用させるため、少なくとも年1回は調節麻痺下の屈折検査を行う。
参考文献
- 今日の眼疾患治療指針第3版
- あたらしい眼科Vol37,No8,2020
関連記事