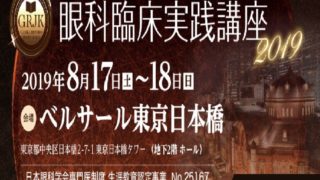今回の記事は眼科臨床実践講座2019のぶどう膜炎の前眼部所見の見極めをまとめた記事です。今回の講演は東京医大の後藤浩先生です。
ぶどう膜炎の原因は多種多様で患者数の上位はサルコイドーシス(13.3%)、原田病(6.7%)、ベーチェット病(6.2%)、細菌性眼内炎(3.8%)、ヘルペス性虹彩炎(3.6%)と続きます(2007年の後藤先生ら調べ)
実際、ぶどう膜炎は疾患特定が可能なものは61%で、そのうち感染性ぶどう膜炎が占める割合は16%です。ぶどう膜炎の診断では問診、全身検査、経時的観察などを行うが、眼内の炎症所見の観察・評価・記録がもっとも重要である。
ぶどう膜炎の診断につながる眼所見は、角膜後面沈着物(KPs)、前房炎症、虹彩、隅角などがあるが、今回の講座では前2つが取り上げられている。
もくじ
1.角膜後面沈着物(KPs)
KPsは細隙灯顕微鏡で最初に気づく異変で、炎症細胞・細胞残渣・色素から構成される。通常は重力の関係でKPsはArltの三角を呈する。そんなKPsは各ぶどう膜炎に特徴がある。
- 下方中心の微細な白色KPs→特異性なし
- 大きく、大小不同の豚脂様KPs→肉芽腫性ぶどう膜炎(サルコイドーシスなど)
※ただし、治療の過程で小さくなることもある。
※サルコイドーシスを示唆する所見は他にもKoeppe結節、Busacca結節、隅角結節、PAS、BHLなどがある。
- 数が少ない(countable )、小さな豚脂様KPs→Posner-Schlossman症候群
※Posner-Schlossman症候群を示唆する所見は他にも患眼の隅角色素減少などがある。
- 豚脂様で整然とした配列を示すKPs→ヘルペス性虹彩炎
※ヘルペス性を示唆する所見は他にも色素を含んだKPs(虹彩にある色素を貪食したマクロファージが色素を貪食するため。)、虹彩の萎縮などがある。
- 輪状に配列したKPs(coin lesion)→CMV虹彩炎あるいはCMV角膜内皮炎
※CMV角膜内皮炎を示唆する所見は他にもCMVなどがある。
- 上方まで分布する小さなKPs→Fuchs虹彩異色性虹彩毛様体炎
※Fuchs虹彩異色性虹彩毛様体炎を示唆する所見は他にも虹彩の萎縮、白内障(後嚢下→成熟)などがある。
- 棘状・網目状で微妙に汚らしいKPs→眼内リンパ腫(特に再発時)
2.前房蓄膿
前房蓄膿は炎症細胞が下方隅角に沈殿したもので、まずは感染症がないかを考える。次にベーチェット病、急性前部ぶどう膜炎、極めて稀に悪性腫瘍の可能性を考える。
- 二ボーを形成し、サラサラで崩れ易い前房蓄膿→ベーチェット病
- 盛り上がった前房蓄膿、線維素析出→急性前部ぶどう膜炎
- 偽前房蓄膿→悪性リンパ腫、成人T細胞白血病
おわりに(個人的感想)
前眼部所見に特化した講義はなかなかなく、体系的に整理することができた。僕のような経験が浅い医師は前眼部所見だけで診断するのは難しい。
関連記事