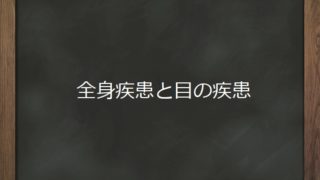もくじ
先天梅毒
先天梅毒とは
経胎盤感染により、流産・死産等の原因となるが、母の感染期間が長く、未治療の場合その発生率は高くなる。胎児に感染するのは胎生5カ月以降で、それ以前は胎盤を通過しにくいとされる。
胎児梅毒、早発性と晩発性先天梅毒
0.胎児梅毒
死産ないし生後間もなく死亡することが多い。
1.早発性先天梅毒
早産時や低出生体重児に多く、2歳以前に結膜皮膚症状、骨病変、肝脾腫、リンパ節腫脹などを認める。
2.晩発性(後天性)先天梅毒
2歳以降(主に学齢期から思春期にかけて)にHutchinson三徴(Hutchinson歯牙、角膜実質炎、内耳性難聴)がみられる。骨病変、神経病変や肝脾腫を伴うことがある。
先天梅毒の眼症状
学童期以降にびまん性角膜実質炎が起こる。始まりは角膜周辺実質に生じる斑状混濁であり、後に角膜全体へ広がり、すりガラス状になる。最終的に血管侵入を伴った瘢痕性の深部角膜混濁を生じる。瘢痕期は、角膜実質層の血管侵入や血行のないghost vessel, retrocorneal hyaline ridgeなどがみられる。

また、前部ぶどう膜炎症状をきたすこともある。早発性先天梅毒の約5%の頻度でぶどう膜炎、特に網脈絡膜炎を生じる。虹彩毛様体炎に併発した白内障や続発緑内障を認めることがあるが、多くは眼疾患に気づかれず落ち着く。眼底は色素集積を伴った網膜色素上皮の萎縮所見である“ごま塩状”の変化を中間周辺部から周辺部にかけて認めることが多い。
ペニシリン治療が行われる現在では活動性のある角膜実質炎をみることは少なく、実質炎後の角膜瘢痕が臨床上散見される。
後天梅毒
後天梅毒の症状
後天梅毒の眼症状は第2期梅毒で認める。ぶどう膜炎(最も頻度が高く、第2期梅毒の約5%)、結膜炎、角膜実質炎、強膜炎、視神経網膜炎などを認める。しかし、特徴的な所見が乏しく、症状は多彩である。
梅毒によるぶどう膜炎
- 虹彩毛様体炎:豚脂様角膜後面沈着物(KPs)を伴う肉芽腫性が多いとされる。
- 網脈絡膜炎:約半数は両眼性で、びまん型と限局孤立型がある。びまん型は後極部から赤道部にかけて硝子体炎や網膜血管炎を伴った滲出性病変がみられる。滲出性病巣は消退するが、時に色素沈着を認め、血管の白線化や視神経萎縮をきたす。血行性にトレポネーマが運ばれ、血管壁及び周囲に炎症性変化を起こす。その結果、網膜血管炎は静脈だけでなく、動脈にも炎症を認めることが多い。時に動静脈閉塞をきたすことも。限局孤立型は主に黄斑部にみられ、硝子体炎を伴う。漿液性網膜剥離や乳頭炎、網膜血管炎を合併することもある。
梅毒の検査と診断
先天梅毒の検査
TP抗原法とSTS法を行い、治療が必要になるのは両検査が陽性の場合のみである。ただし、その他の場合も感染初期の恐れがあるため、経過観察を行い、適宜治療を開始する場合がある。また、先天梅毒では、母体から移行したIgG抗体があるため、IgM-FTA-ABS抗体測定が診断に必要となる。しかし、IgM抗体は感染後2~3週間で陽性となり、4~5週でピークとなる。よって、IgM抗体は出生直後の診断には向かないが、治療によって低下するため、治療効果の判定に有用である。
梅毒による眼症状の診断
両眼性の角膜深部への血管侵入を伴う角膜炎をみたら、梅毒性角膜実質炎を必ず考慮する。
梅毒の治療
治療は下記参考に記載する所見を認めた場合に、先天梅毒としてペニシリン投与を行う。視神経炎や嚢胞様黄斑浮腫あればステロイドを併用することがある。角膜瘢痕が強ければ角膜移植を考慮することもある。
- 角膜実質炎合併⇒ステロイド点眼を併用
- 前部ぶどう膜炎合併⇒散瞳薬点眼を併用
先天梅毒の治療基準
- 梅毒の活動所見を認める
- 髄液にて細胞数・蛋白増加・STS陽性を認める
- 児STS抗体価≧母体STS抗体価×4
- 児のIgM-FTA-ABS抗体が陽性
梅毒治療の治療効果判定
STS定量において抗体価が
- 8倍以下あるいは初期値の1/4以上の低下
- 2桁までの抗体の低下
で治療効果ありと判定する。
参考文献
- クオリファイ5全身疾患と眼(専門医のための眼科診療クオリファイ)
- 眼科学第2版
- Clinical features of anterior uveitis caused by three different herpes viruses
関連記事