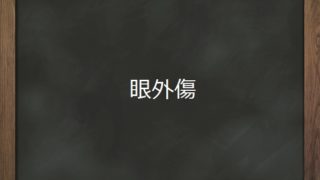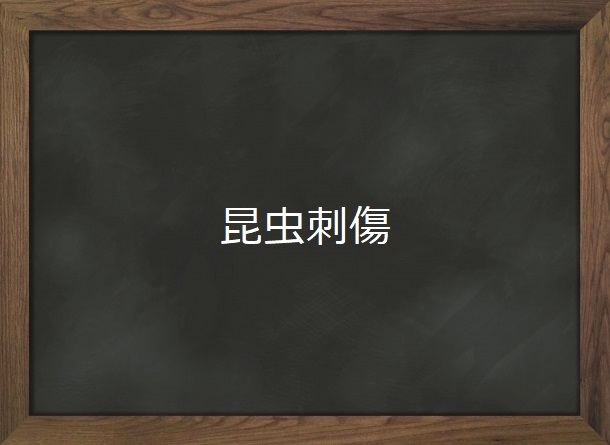昆虫刺傷は昆虫に刺されることで生じる刺し傷だが、日本では毒毛虫と蜂による眼障害が報告されている。
もくじ
毒毛虫による眼障害
1.毒毛虫による眼障害とは
毒毛虫は毒針毛を持ち、その毛は水・酸・アルカリに不溶性のキチン質で、微量のヒスタミンと酵素を含んでいる。表面に尖端と逆向きの返しが付いており、刺さると眼瞼や眼球の動きで組織の中を前進する。その異同は数年間が経過すると棘が溶けて移動が止まる。この毛が仮に侵入した場合には、数年の経過でキチン質が溶け構成蛋白が露わになり、重篤なぶどう膜炎を発症する。
2.毒毛虫による眼障害の診断
診断のためには毛虫との接触歴が重要になるが、接触したことがなくても、その毛を確認することができる。眼瞼や角膜、前房に毒針毛がある場合には硝子体への侵入がないかを必ず確認する必要がある。
3.毒毛虫による眼障害の治療
治療として、眼瞼皮膚に毒針毛があれば、末端が露出している毛だけを無鉤鑷子で引き抜く。さらに、ステロイド眼軟膏と抗菌眼軟膏を刺傷部位に1日数回擦り込まないように塗布する。再診時のときに皮膚から浮き上がった毒針毛を抜き続ければ、1カ月で瘢痕を残さず治癒する。結膜や角膜の毒針毛は結膜異物や角膜異物抜去時と同様に行う。硝子体中の毒針毛は、硝子体混濁がないうちに硝子体手術で摘出する。
蜂刺傷
1.蜂刺傷とは
蜂に刺されても1度で生命の危機にさらされることはほとんどないが、眼球にとってはそれが致命的になる。特に、スズメバチの毒液は強力で、毒液を浴びるだけで失明に至るケースもある。スズメバチの針は約7.0㎜とされ、刺す部位によっては硝子体に達する恐れがある。
2.蜂刺傷の診断
眼瞼、眼球を刺されたかどうか問診すると同時に、眼前を飛んだだけでも毒液が飛入している恐れもあるため、細隙灯顕微鏡で眼球損傷の有無を確認する必要がある。
3.蜂刺傷の治療
スズメバチ毒液飛入の場合は化学傷として処置をするが、眼内に浸潤あるいは刺入した場合は眼内組織を破壊し続ける。中和液は現時点で存在しないため、できる限りの希釈を行う必要がある。できるだけ速やかに眼内潅流液を用いて、前房洗浄や硝子体内洗浄などを行う。
これと同時に、炎症性二次障害を防ぐため、ステロイドの結膜下注射と点眼を頻回に行う。点滴や内服は眼内へ移行しづらい。なお、スズメバチの刺傷跡は治癒までに1か月以上かかることがある。刺傷部位にステロイド眼軟膏、抗菌眼軟膏を1日数回塗布し、冷罨法、局所の安静を保つ。
参考文献
関連記事