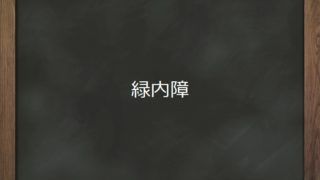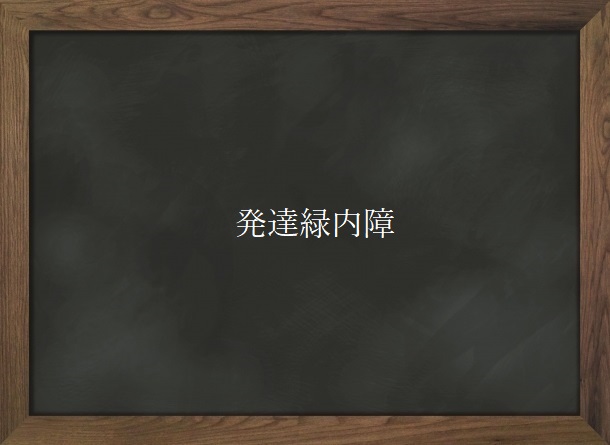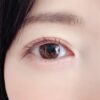発達緑内障(小児緑内障)とは
先天的な隅角の発達異常により眼圧上昇をきたし、緑内障となっている状態である。発達異常の部位が主に隅角に限局しているものと、他の部位の発達異常を伴うものがある。現在は小児緑内障と呼んでいる。
World Glaucoma Association(WGA)における小児緑内障の診断基準
緑内障の診断基準(2項目以上)
- 眼圧>21mmHg(全身麻酔下であればあらゆる眼圧測定方法で)
- 陥凹乳頭径比(C/D比)増大の進行、C/D比の左右非対称の増大、リムの菲薄化
- 角膜所見(Haab線または新生児では角膜径11mm以上、1歳未満では12㎜以上、すべての年齢で13㎜以上)
- 眼軸長の性状発達を超えた伸長による近視の進行、近視化
- 緑内障性視神経乳頭と再現性のある視野欠損を有し、視野欠損の原因となる他の異常がない
緑内障疑いの基準(1項目以上)
- 2回以上の眼圧測定>21mmHg
- C/D比増大などの緑内障を疑わせる視神経乳頭所見がある
- 緑内障による視野障害が疑われる
- 角膜径の拡大、眼軸長の伸長がある
若年開放隅角緑内障(JOAG)の診断基準
- 4歳以降に発症する小児緑内障
- 眼球拡大を伴わない
- 先天性の眼形成異常や全身疾患を伴わない
- 開放隅角で、正常隅角所見
- 小児緑内障の診断基準を満たす
1.早発型発達(小児)緑内障
3歳以下に発症する発達緑内障である。以前は原発先天緑内障と呼ばれていた。発症頻度は10000-32000人に1人で、男児に多く、両眼性のことが多い。
主な所見
典型例は眼圧上昇による角膜径拡大(牛眼という。正常新生児9.5-10.5mm、1歳で11-12mmである。1歳以下で12mm以上の場合は注意する。)、角膜浮腫、Descemet膜破裂(所見はHaab’s striaeという。この所見があると術後視力発達不良となる。)、虹彩軽度萎縮を認める。眼圧は一般的に高く、隅角は分化不全を示す。虹彩の付着部位の異常が代表的とされる。視神経乳頭は成人より陥凹が深く、同心円状の拡大が特徴的とされる。
その他所見
1.前房深度
前房深度は浅いのが正常で、成人のように深々している場合は異常である。
2.眼圧測定
小児の眼圧は催眠下や全身麻酔下であるため、成人の値よりも低くなる。そのため、正常上限は21mmHgではなく、15mmHgとするのが良い。
3.隅角検査
角膜混濁のため透見できないこともある。正常乳幼児では、隅角はやや狭く、recess形成はない。線維柱帯は成人より平滑で透明である。一方で、早発型発達緑内障では、隅角底が広くて深く、虹彩付着異常を伴うことが多い。
4.眼軸長
眼軸長に左右差があれば、長眼軸眼の視機能発達は不良となりやすい。
5.視神経乳頭
陥凹拡大の有無を観察する。治療効果があれば陥凹は小さくなることが多い。
角膜実質よりもDescemet膜は弾性が低いため、伸展力に耐えられず破裂し、その結果角膜実質浮腫、角膜混濁となる。
Descemet膜断裂の鑑別
鉗子分娩による断裂:左眼に好発し、眼球の垂直経線方向に走る。
Haab’s striae:輪部に対して同心円状、水平・垂直方向など、どのような走行も取りうる。
治療
薬物治療は無効なため、診断したら早急に手術加療(線維柱帯切開術or隅角切開術)を行う。いずれにせよ眼圧コントロールは80%程度である。
線維柱帯切開術は角膜混濁があってもできるが、将来的に線維柱帯切除術が困難になる点、強膜壁画菲薄化し穿孔しうる点などが課題になる。一方で、隅角切開術は角膜混濁があると行えないが、Schlemm管の同定が不要で、結膜温存可能であるメリットがある。
2.遅発型発達(小児)緑内障
隅角形成異常が軽度なため発症が遅れることに加えて、末期まで自覚症状がないこともあり、片眼性の場合は特に発見が遅れてしまう。
診察所見は早発型とほとんど同様だが、角膜径は正常、Haab’s striaeがない、前房深度は深い点が異なる。
治療は成人の開放隅角緑内障に準じて行うが、薬物治療は反応性が悪いことも多い。初回は下方からの線維柱帯切開術を行うのが良いとされる。
3.他の先天異常を伴う発達(小児)緑内障
無虹彩症、Sturge-Weber症候群、Axenfeld-Rieger症候群などがある。
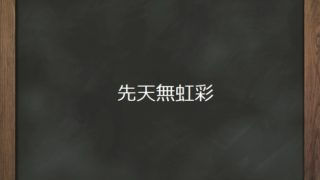
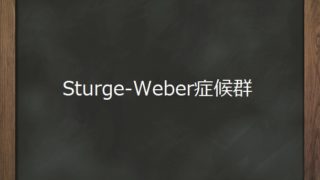
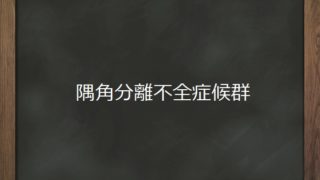
参考文献
関連記事