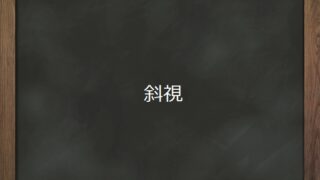もくじ
間欠性外斜視とは
片眼が固視目標を注視しているときに、他眼が外側へ偏位している外斜視の状態と、両眼とも固視目標を注視して顕性の外方偏位が現れない外斜位の状態が合併している斜視のことを間欠性外斜視という。
日本人成人における間欠性を含む外斜視の頻度は1.7%であり,そのうち60%以上が輻湊不全型であるとされる。また、小児期の斜視のうち最も多く、小学生の約0.14%にみられる。長期で観察すると、約10%で自然治癒、約40%は変化なし、残り50%は時間経過とともに恒常性外斜視に悪化するものもある。
間欠性外斜視の症状
幼児期~約8歳までに発症し、3~5歳頃以降の発症が最も多いとされる。初期には融像性輻輳により、遠見でも近見でも斜位を維持しやすいが、疲労時、体調が悪い時、起床直後には外斜視になりやすい。発症時期の年齢が比較的若いため、感覚適応が起こり、小児では複視を自覚しない。
斜位時の眼位は良好であるため、両眼視はほぼ正常に発達する。しかし、中には乳幼児期に発症し、偏心固視による異常網膜対応のため単眼固視症候群となるため、軽度の弱視も約5%の症例に見られる。
間欠性外斜視の分類
- 基礎型:遠見と近見の眼位の差が10Δ以下
- 輻輳不全型:近見眼位のほうが10Δより大きい
- 開散過多型:遠見眼位のほうが10Δより大きい
間欠性外斜視の診断と評価
- 融像除去のため片眼を30分以上遮閉する。この時、近見斜視角が増加、遠見=近見となれば基礎型である。
- 遮閉で近見斜視角が変化しないなら、両眼に+3.00Dのレンズを装用する。この時、近見斜視角に変化なければ真の開散過多型で、近見斜視角が増加すれば高AC/A比である。
また、間欠性外斜視がどのくらいコントロールできているか評価を点数化する方法が提唱されている。
Newcastle Control Score(NCS)では、遠見や近見に加え、家庭での眼位逸脱頻度を各0~3点で評価し、合計点で制御状態を数値化する。
Newcastle Control Score
| 家庭 | 点数 |
|---|---|
| 斜視/片目つぶり なし | 0 |
| 斜視/片目つぶり 50%以下(遠見) | 1 |
| 斜視/片目つぶり 50%以上(遠見) | 2 |
| 斜視/片目つぶり 遠見・近見 | 3 |
| 病院 近見 | 点数 |
|---|---|
| 遮閉後,すぐに融像 | 0 |
| 遮閉後,瞬目・固視で融像 | 1 |
| 遮閉後,戻りなし | 2 |
| 自然に顕性斜視,戻りなし | 3 |
| 病院 遠見 | 点数 |
|---|---|
| 遮閉後,すぐに融像 | 0 |
| 遮閉後,瞬目・固視で融像 | 1 |
| 遮閉後,戻りなし | 2 |
| 自然に顕性斜視,戻りなし | 3 |
Mayo Clinic Control Score(MCCS)では、遠見および近見での斜視出現と回復の速度、持続時間に基づいてそれぞれ0~5点で評価する。
Mayo Clinic Control Score
| 点数 | 評価内容 |
|---|---|
| 5 | 30秒以上の恒常性外斜視 |
| 4 | 遮閉前の30秒間の観察中,外斜視の時間 >50% |
| 3 | 遮閉前の30秒間の観察中,外斜視の時間 <50% |
| 2 | 遮閉(10秒間)しなければ外斜視にならない,斜位へ戻る時間 >5秒 |
| 1 | 遮閉(10秒間)しなければ外斜視にならない,斜位へ戻る時間 <5秒 |
| 0 | 遮閉(10秒間)の遮閉後,斜位へ戻る時間 <1秒 |
そのほか、診察時の遠見・近見の観察結果を0~10点で合算するOffice-Based Control Scoreや、遠方注視を10秒間行って斜視の出現・回復の様子を0~4点で評価するLACTOSEなどがある。特に小児例やコントロールが不安定な症例では、来院時間や活動後の状態、疲労度なども考慮し、複数回の評価による総合的判断が重要である。
間欠性外斜視の治療
1.光学的治療
斜視が顕在化していない症例や小角度の外斜視で、複視やぼやけ、眼精疲労を生じる症例など下記条件を満たす場合にプリズム眼鏡装用や、調節性輻輳を誘発して斜位を維持する過矯正眼鏡装用などを行う。しかし、最も有効な治療は2の手術治療である。
- 斜視が顕在化していない
- 複視やぼやけ、眼精疲労を生じる
- 斜視角が小さい
- 視能矯正も斜視角が25Δ未満
- 微小斜視や単眼固視症候群などの合併がない
- 近見立体視がある
↓プリズム眼鏡療法についてはまずこちらをご覧ください。
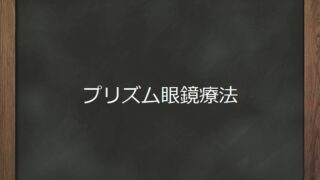
1.小児の間欠性外斜視に対する眼鏡処方
多くは斜視角が増加することがない。そのため、眼位・立体視力が維持され、恒常性への移行や両眼視機能の低下例以外では斜視手術は必要ではない。
よって、小児の間欠性外斜視に対する眼鏡処方の適応は下記の通りである。
- 屈折異常、不同視、弱視による屈折矯正を必要とする症例
→近視、乱視、不同視は外斜視の増悪因子で、これらが原因で遠見でのぼやけが生じ、融像性輻輳が起きにくくなる。適切な眼鏡を処方し、両眼視機能を安定させれば、斜視が顕在化しにくくなる。また、感覚性外斜視への進行を防ぐため、弱視の場合は弱視治療も併せて行う。 - 複視や眼精疲労、近見時のぼやけを訴える症例
→近業作業を長時間行うことによって起こる場合が多い。輻輳不全型の外斜視で起こりやすいとされる。
また、小児の場合は成長に伴って度数や瞳孔間距離が変動するため、組み込みプリズム眼鏡ではなく、膜プリズムを処方することが多い。
2.成人の間欠性外斜視に対する眼鏡処方
近業作業時の調節幅が同年齢の正常者に比べ低下しており、近業作業を続けると疲労やぼやけが生じやすいと考えられる。また、輻輳不全や老視による近見障害が原因の場合もある。
よって、眼鏡を処方する際には、屈折検査や眼位検査に加えて、立体視力や調節力、輻輳検査などを行い、プリズム眼鏡と中距離や近距離での視力矯正を加えた眼鏡処方が必要である。
比較的大角度の眼位ずれがあり、両眼視時に著明に近視化する状態を斜位近視という。著明な近視化のため像のぼやけ、強い眼精疲労を訴える。この治療は眼位矯正で、大角度の場合は斜視手術だが、小角度の場合はプリズム眼鏡を装用する。
2.手術治療
大角度の外斜視や外方偏位の頻度が高い外斜視に対しては、手術治療が選択される。具体的な手術としては外直筋後転術と内直筋短縮術を組み合わせて行う。基礎型と開散過多型には両外直筋後転術が適応となり、輻輳不全型には両内直筋短縮術や片眼の前後転術、両外直筋後転術などを行う。
術後に内斜視へと移行するリスクが5歳未満の小児で高いことを指摘されており、その観点からは5歳以降での手術が望ましいとされる。また、術後に眼位が戻る可能性を見越して意図的に過矯正を行う場合には、複視の影響が学習や日常生活に支障をきたしにくい10歳未満での実施が推奨される。
間欠性外斜視の予後
成人の症例では術後戻りは少ないが、小児では10~25Δの術後戻りがありうるため、術直後の眼位を10Δ以内の内斜視になるよう、あえて過矯正することが多い。
参考文献
- 今日の眼疾患治療指針第3版
- あたらしい眼科Vol37,No8,2020
- 小児眼科・弱視斜視外来ノート
- Jampolsky A : Management of exodeviation.
Strabismus symposium of the New Orleans Academy of Ophthalmology (Burian HM et al eds), p140–156, Mosby, St Louis, 1962 - The prevalence and types of strabismus, and average of stereopsis in Japanese adults
- Grading the severity of intermittent distance exotropia: the revised Newcastle Control Score
- An office-based scale for assessing control in intermittent exotropia
- LACTOSE control scoring helps predict surgical outcomes for childhood intermittent exotropia
関連記事