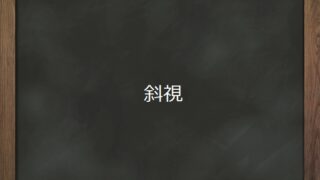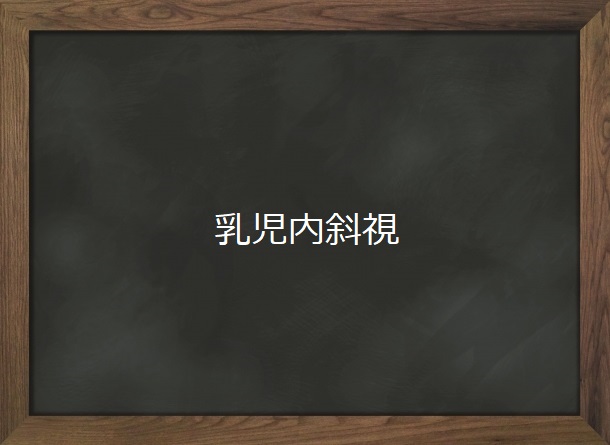乳児内斜視とは
本態性乳児内斜視は生後半年までに大角度(30Δ以上)の恒常性内斜視を発症する。治療が遅れる、あるいは視覚管理が不適切な場合は、網膜対応異常や偏心固視弱視をきたすリスクも上がる。しかし、眼位ずれが間欠性であったり、調節性で近見性の輻輳が関与していたりする場合には、両眼視機能の予後は比較的良好である。
乳児内斜視の診断
下記の臨床特徴のうち①~④がポイントとなる。特に、斜視角が45Δ以上の例で、写真判定も含めて生後6カ月以前の発症が確認されれば本態性の可能性が高い。斜視角が中等度までであれば眼位の正常化が遷延する恐れがあり、恒常性斜視の確認を目的に複数回眼位検査を行う。また、アトロピン硫酸塩による調整麻痺条件下での遠視度数をもとに処方した完全矯正眼鏡の装用にて、眼位改善の有無を確認する。
本態性乳児内斜視の臨床特徴
- 生後6カ月以前に発症
- 斜視角が大きい(30Δ以上)
- 恒常性で斜視角の変動が少ない
- 中枢神経の異常がない
- 交叉固視
- 調節因子の関与がない:アトロピン点眼や遠視矯正眼鏡装用に反応しない
- 上下眼位ずれの合併:交代性上斜位(40%)や斜筋異常
- 潜伏(40%)または顕性潜伏眼振の合併
- 視運動性眼振の向きが鼻側方向で優位
- 下斜筋過動(60%)
乳児内斜視の治療
乳児内斜視に対しては眼位未矯正期間あるいは顕性斜視期間を短縮することが、両眼視機能獲得のために重要である。
まずは調節麻痺薬を用いて、屈折異常がないかを確認する。乳児でも早期発症の調節性内斜視のこともあり、+2.0D以上の遠視であれば眼鏡で完全屈折矯正を行う。しかし、眼位異常がない、屈折矯正でも10⊿以上の内斜視が残れば手術適応とする。乳児内斜視は斜視角も大きいことが多いため、原則として超早期の手術矯正が必要となる。
初回手術を生後8カ月以前に行うことを超早期手術、2歳までに行うことを早期手術という。超早期手術は術直後より正位または斜位で経過する例が多く、少なくとも融像能ならびに周囲立体視獲得には有利と考える。一方、早期手術も結果は良好かつ安定した眼位および両眼視機能の獲得に有効である。具体的な手術内容については省略するが、斜視角に応じて両眼または片眼の内直筋後転術を行う場合がある。
乳幼児期は視覚発達期であり、複視や混乱視などの感覚異常に対して代償性の適応が機能しやすい。特に、乳児内斜視においては、交叉固視または交代固視の状態にある眼位矯正前より、術後、小角度の斜視や斜位になると抑制や偏心固視などのリスクが上がる。また、40Δ以上の大角度を示した症例では自然軽快はほとんどないことにも留意する。
固視動揺が見られる場合は優位眼遮蔽の併用を、また、8〜10Δ以上の残余斜視に対しては膜プリズム装用を行う。また、上下斜視、斜筋異常が顕在化した場合には、手術を検討する必要がある。
参考文献
- 今日の眼疾患治療指針第3版
- あたらしい眼科Vol37,No8,2020
- あたらしい眼科 Vol38,No.10,2021
- 小児眼科・弱視斜視外来ノート
関連記事