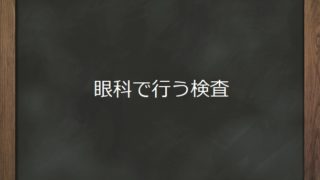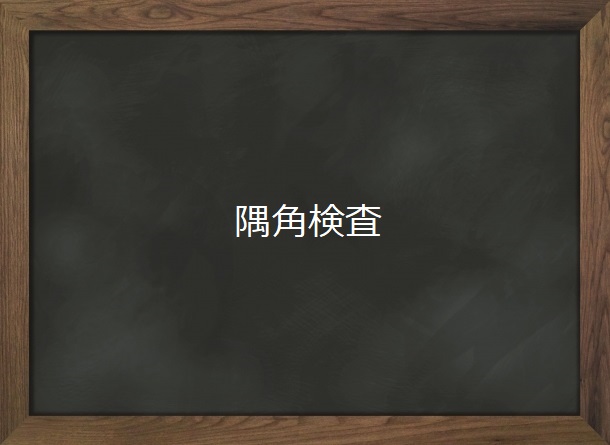と疑問をお持ちの方の悩みを解決できる記事になっています。
隅角検査のまとめ
- 隅角検査は緑内障の診察や隅角に異常が出うる疾患に対して行う。
- 隅角検査には直接型と間接型があり、一般的には間接型が行われる。
- 狭隅角眼は通常の隅角検査で観察できないので、圧迫隅角検査を行い隅角を観察する。
- 隅角開大度はShaffer分類やScheie分類によって分類する。
- その他にも、色素沈着や周辺虹彩前癒着などの異常所見を観察することができる。
隅角検査とは
隅角検査は房水流出路である隅角を観察するための検査である。
検査対象は下記の通りである。
隅角検査の検査対象
- 緑内障の診察(緑内障病型検査や治療方針の決定、手術後の房水流出路の評価など)
- 隅角に異常が出うる疾患(血管新生緑内障、ぶどう膜炎、鈍的外傷、白内障や緑内障などの術後など)
隅角検査の原理と特徴
隅角検査は接触型レンズを用いて隅角を観察する。直接型と間接型があるが、間接型が主に行われている。
1.直接型検査法
直接型検査法は直接型隅角鏡(Koeppe型、Barkan型、Swan-Jacob型など)を用いて行う。患者を仰臥位にした後、直接型隅角鏡を装着し、手持ち細隙灯顕微鏡や手術陽顕微鏡などを用いて観察する。乳幼児の隅角検査や隅角癒着解離術のような手術時に行う。
2.間接型検査法
間接型検査法は一般的に行われる隅角検査であり、間接型隅角鏡(Goldmann隅角鏡、Zeiss四面鏡、Sussman型など)を用いて行う。間接型検査法では細隙灯顕微鏡を用いて行う。反射鏡が上にある場合は下方隅角、下にある場合は上方隅角を観察していることに注意する。
ミラーイメージであるため、四面鏡など複数ミラーがある場合には隣り合うミラー所見が連続しないことに注意する。
隅角検査の検査法
- 点眼麻酔を行う。
- スコピゾル®を隅角鏡接眼部に付ける。
- 角膜に隅角鏡を乗せる。
通常、この手順で観察する。
ただし、Sussman型やZeiss型隅角鏡では、角膜との接触面積が小さいので、スコピゾル®は不要である。
1.静的隅角検査
- 暗室下で細隙灯顕微鏡の光量を極力下げる
- 瞳孔領に光を入れない
- 隅角鏡で眼球を圧迫しない
- 第一眼位
この自然瞳孔の状態での隅角開大度を評価する。用いる隅角鏡によって所見の取れ方が異なるので、この検査は主観的な検査ということになる。
2.動的隅角検査
動的隅角検査は静的隅角検査の後に引き続き行う。
- 細隙灯顕微鏡の光量を上げたり、瞳孔領に光を入れて縮瞳させる。
- 隅角鏡または眼位を傾斜させて軽度圧迫を加える。
これらによって隅角を開大させて、隅角底を観察する。
圧迫時に開放しない場合はプラトー虹彩の可能性があります。プラトー虹彩は瞳孔縁で水晶体による虹彩隆起があり、周辺部では前方回旋した毛様体による虹彩隆起を認めることがあります。これをdouble hump signと言います。また、急性閉塞隅角緑内障や一部の可逆的な閉塞では隅角が一時的に開放することがあります。
3.圧迫隅角検査
圧迫隅角検査は動的隅角検査の一種である。Sussmann型やZeiss型のような接触面積が小さいレンズを用いて、角膜中央を圧迫して観察したい隅角へ押しやる。すると房水が移動し、周辺部虹彩を後方に押し下げ、隅角底を観察することができる。特に、通常の隅角検査で観察できない狭隅角眼の観察する手技である。
隅角検査の評価
隅角検査では以下を評価する。
1.隅角開大度
隅角開大度の評価は下記の3つの評価方法が一般的である。
- Shaffer分類:隅角の広さ(隅角線維柱帯と周辺虹彩のなす角度)
- Scheie分類:隅角の深さ(隅角構造のどの部分まで観察可能か)
- Spaeth分類:隅角の形状
1.Shaffer分類(隅角線維柱帯と周辺虹彩のなす角度)
- Grade0(閉塞隅角):Angle0
- Grade1(狭隅角):Angle10°
- Grade2(狭隅角):Angle20°
- Grade3~4(開放隅角):Angle20~45°
2.Scheie分類(隅角構造のどの部分まで観察可能か)
- Grade0:線維柱帯、強膜岬、毛様体帯の全てが見える。
- GradeⅠ:強膜岬が見えるが毛様体帯が見えにくい。
- GradeⅡ:強膜岬は見えず、線維柱帯の下半分が見えにくい。
- GradeⅣ:線維柱帯が見えず、Schwalbe線まで虹彩が隠れている。
3.Spaeth分類
- 隅角の角度:10、20、30、40度
- 虹彩周辺部の形状:s(steep:急峻な凸状)、r(regular:平状)、q(queer:凹状)
- 虹彩の付着部位:A(Schwalbe線より前方に付着)、B(Schwalbe線より後方に付着)、C(強膜岬に付着)、D(毛様体より付着)、E(毛様体のかなり深い部位に付着)
2.色素沈着(Scheie分類)
隅角部、特に線維柱帯の色素沈着は正常若年者にはほとんど認められないが、加齢とともに増加する。通常は下方隅角に最も強く、上方で弱い。隅角部の色素沈着の程度により、NONE~Ⅳ度の5段階に分類される。
また、落屑緑内障では色素沈着が強く、Schwalbe線ないしそのやや前方に波状の色素沈着(Sampaolesi線)を認めることがある。また、Posner-Schlossman症候群では患眼隅角の脱色素を認めることがある。
3.その他の異常所見
A.周辺虹彩前癒着(PAS)
周辺虹彩前癒着(PAS)は隅角部と周辺部虹彩が癒着した状態で、その形状はテント状、台形状、広範な癒着などがある。
周辺虹彩前癒着が生じる疾患とPASの特徴
- 原発閉塞隅角緑内障:テント状、台形状、広範なPASなど
- 血管新生緑内障:血管新生(+)を伴うPAS
- ぶどう膜炎:テント状、台形状のPASなど
- ICE症候群:角膜まで達する広範に癒着したPAS
- アルゴンレーザー:照射部位に一致したテント状のPAS
- 内眼手術後:創口に向かう、さまざまな形態のPAS
など
B.隅角結節
虹彩や隅角部に観察される白色塊状の小結節を隅角結節という。サルコイドーシスなどの肉芽腫性ぶどう膜炎で見られる。
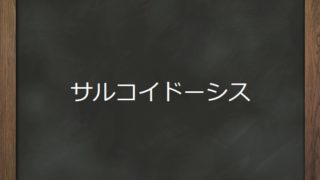
C.隅角後退
鈍的外傷の程度により程度は異なる。
D.血管新生
眼虚血性病変があると新生血管を生じることがある。ただし、隅角には生理的な血管も存在するため、新生血管かどうかには鑑別が必要となる。
生理的血管は、虹彩周辺部で線維柱帯と平行に走行したり、毛様体前面を横切るように走行したりする。また、血管は比較的短くて太く、分岐することはまれである。
一方、新生血管は毛様体前面から線維柱帯付近まで達すること、分岐すること、PASを伴うことが多い
E.隅角形成不全
発達緑内障では、強膜岬に近い毛様体から線維柱帯のやや上方辺りにかけての位置に虹彩が付着して線維柱帯を確認できないことがある。また、Axenfeld-Rieger症候群では索状膜状の虹彩組織やSchwalbe線肥厚(後部胎生環)を認める。
F.炎症性滲出物
隅角結節は白色の小球状の結節性病変で、眼サルコイドーシスに特徴的である。
参考文献
- 今日の眼疾患治療指針 第3版
- 眼科検査ガイド
- あたらしい眼科Vol.42,No.5,2025
関連記事